
エッセイ:「きく」と「みる」
中里信和
2025.3.27 Thu
私は音楽を「きき」ながらの仕事が大好きです。でもスピーカが安物で、友人には笑われました。彼の自宅のオーディオルームには巨大なスピーカがあり、音源はアナログ・レコードです。ビル・エバンスの「ワルツ・フォー・デビイ」をかけてもらい、うっとり「きき」ほれていたら、途中で曲が止められてしまいました。次に友人はキース・ジャレットの「ケルン・コンサート」をかけました。こちらも私が大好きな曲。でも、すぐにストップ。その次はカラヤンのチャイコフスキー交響曲第6番。これまたすぐにストップ。ようするにその友人はオーディオ・マニアで、「いい音」を自慢したかったのです。一方の私は音質には必ずしもこだわりません。ワインがあれば、AMラジオのエディット・ピアフで十分に幸せになれます。
音質にこだわらないとはいえ、妻とは時々、クラッシックのコンサートに出かけます。オーケストラの迫力のある音が良いから感動するのかと以前は考えていました。しかし最近、テレビや動画配信サイトで感動している自分にも気づきました。音楽を「きく」時には、指揮者や演奏者の様子を「みて」楽しんでいることを。
「きく」と「みる」の関係は科学的にも証明されています。私の専門は「てんかん」です。大脳の一部が興奮し過ぎて、さまざまな「てんかん発作」が生じます。大きな全身けいれんが有名ですが、ほかにも「きこえない」はずの音が「きこえる」発作や、「みえない」はずの景色が「みえる」発作もあります。またニオイ、味、身体感覚、感情変化など大脳機能のすべてが「てんかん発作」になりえます。ですから大脳機能の局在診断は、私の研究テーマでもあるのです。
聴覚が専門の川瀬哲明先生(東北大学名誉教授)との共同研究を紹介しましょう。「ベ」の音を「きく」時、同じ「ベ」を発音する口唇を「みて」いると、違う「ゲ」を発音する口唇を「みて」いる時より脳の聴覚野の反応が素早いのです。これとは別に、マガーク効果として知られる意地悪な心理実験があります。「ガ」と話す映像をみながら「バ」の音をきくと「ガ」でも「バ」でもない「ダ」と勘違いして「きこえる」のです。つまり「みる」は「きく」に影響しているのです。アメリカに留学したばかりの私は、相手の口唇ばかりをみつめていて笑われたことがありますが、母国語の日本語ですら、口唇を「みる」ほうがよく理解できます。
文字のない古代の日本でも「きく」という言葉は使われていました。大和言葉ですね。やがて中国から漢字が輸入され、聞く(音をきく)、聴く(言葉をきく)、利く(理論をきく)、効く(気持ちをきく)、訊く(本意をきく)などの漢字が当てられたそうです。「みる」も同様で、複数の当て字があり意味も多様です。多様な「きく」と多様な「みる」を掛け合わせれば、パワーは無限大です。「きく」と「みる」の情報は、脳の連合野という部位で統合されて、ついには「こころ」の世界に入り込むのです。
最後にひとつ、希望のもてる脳の話を紹介しましょう。先天的に耳のきこえない方では、脳の聴覚野は何をしていると思いますか? 最近の研究では、聴覚以外の情報、たとえば骨が感じる振動や皮膚が感じる空気の流れなど音とはいえない情報をかきあつめて、「きく」の仕事をしているらしいのです。同様に、先天的に目の見えない方の脳の視覚野では、点字を読むように代用的な情報をあつめて「みる」仕事をしています。耳もきこえず、目もみえないヘレン・ケラーが、偉大な仕事をなしとげたことは有名です。
「きく」も「みる」も最終的には脳の仕事です。「こころ」のある脳って、素敵ですね。
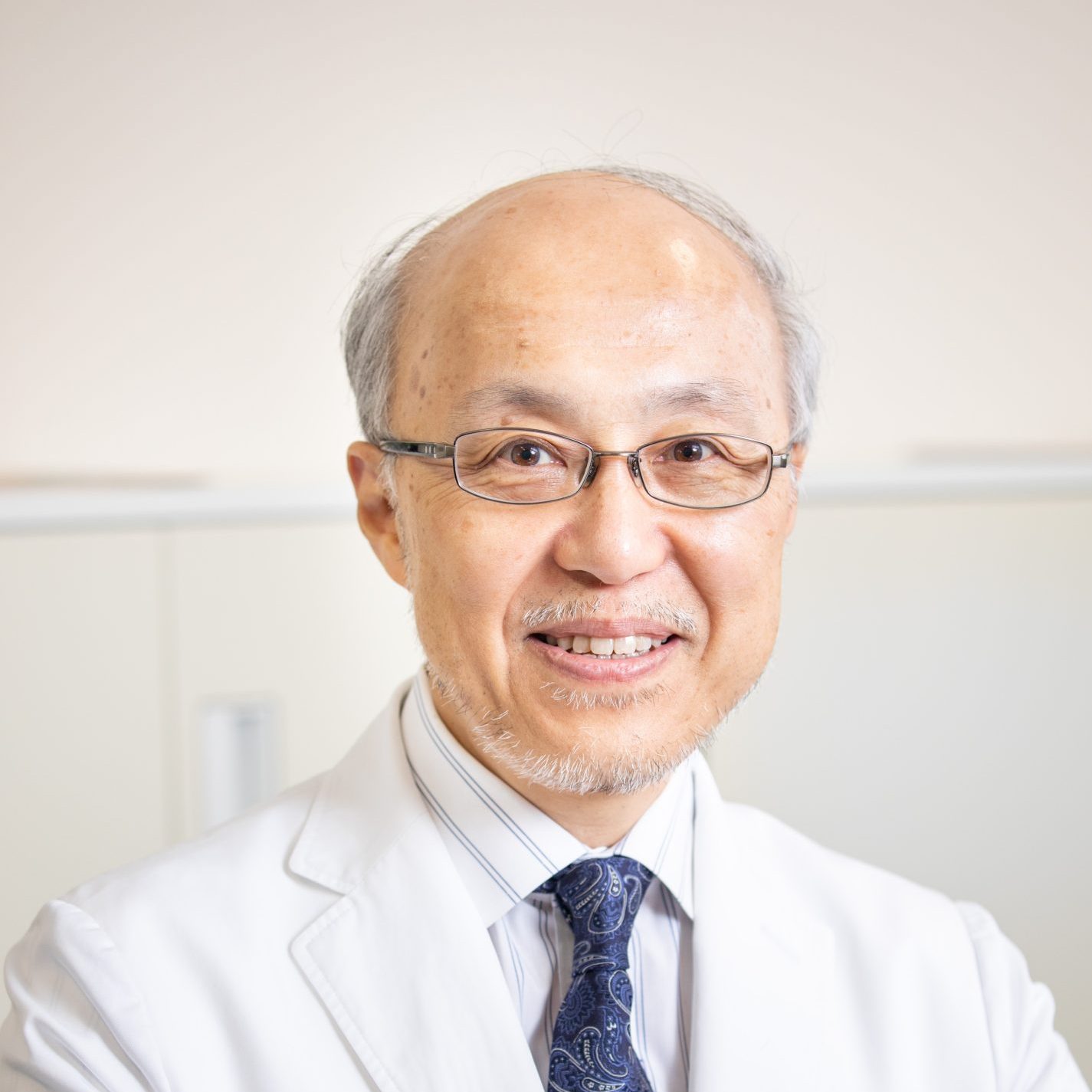
中里信和
Nobukazu Nakasato
岩手県出身。1984年東北大学医学部卒業。同脳神経外科助手、米国カリフォルニア大学ロサンゼルス校医学部・研究員、広南病院・臨床研究部長および副院長を経て、2010年より東北大学大学院医学系研究科てんかん学分野教授、東北大学病院てんかん科長に就任。
- 関連リンク
- 東北大学大学院医学系研究科 てんかん学分野













