
難聴予防などに効果をもたらす酸化ストレス応答機構の活性化が、ヘルシー・エイジングを導く
本橋ほづみ(東北大学大学院医学系研究科 医化学分野 教授)
2025.7.16 Wed
大きな音に晒されるうちに耳の聞こえが悪くなる、騒音性難聴。この聴覚障害は、内耳の感覚細胞が失われてしまうことが主たる原因とされ、一度発症してしまうと完治が難しいため、大切なのは予防である、と言われます。
この騒音性難聴の予防に、生体の酸化ストレス応答を担う制御タンパク質NRF2の活性化が有効である、と報告したのは東北大学大学院医学系研究科医化学分野の本橋ほづみ教授の研究チームです。NRF2を活性化させると、大音量への曝露による酸化ストレス障害から内耳が保護され、聴力低下が起こりにくくなることを明らかにしました。
その研究のお話をきっかけに、本橋教授が取り組まれているテーマについて、そしてまた私たちが健康に歳を重ねてゆくための手がかりについて、お話を伺います。
耳の聞こえが悪くなるのを予防できる可能性がある、という研究結果を得られたというお話ですね。
本橋
まず先に申し上げますと、私たちの研究はヒトではなくマウスの実験が主であり、そして興味の矛先は分子メカニズムにあります。ですから、マウスの耳の聞こえに影響があるような分子メカニズムを調べた、ということです。
長年、遺伝子がどのように制御され、発現し、タンパク質ができるのか、という転写制御1に興味を持ってきました。メンターであった山本雅之先生2の研究室ではNRF2という転写因子が中心的な研究テーマの一つであり、NRF2が酸化ストレスに対する応答機構となって細胞を丈夫にする働きをもつ、ということがわかってきていました。その後、老化をミッション・テーマとする東北大学加齢医学研究所3で独立することになり、転写因子NRF2が強い抗老化作用を持っているらしいという予想はできたものの、きちんとした研究がほぼなかったので、老化の研究をはじめたのです。
単純に言うと、NRF2が活性化した状態では、さまざまな加齢関連の疾患や病態が遅延します。完全に抑制できるわけではありませんが、遅くなる。たとえばヒトは歳を取ると、酒のつまみには乾き物より塩辛のようなとろんとしたものを好みますが、それは唾液腺が老化して唾液の分泌が落ちるから。マウスも同じで、歳を取ると唾液腺が老化して細胞が徐々に減っていきます。ところが、NRF2が活性化した状態ではそれが起こりにくい。酸化ストレスの増加が抑えられ、若いときと同じような状態が維持されます。
そうしたことがわかってきたときに、耳鼻科の香取幸夫先生4や学生たちと「加齢性難聴や騒音性難聴についても調べましょう」ということになり、それでマウスを使って実験をしたところ、NRF2欠損マウスで重篤化し、NRF2を活性化すると症状が軽減されることなどがわかったのです。そういった経緯があってのことですから、耳の研究をメインにしているというわけでは全くなく、「細胞をどう良い状態に保っていくか」の研究から派生した結果のひとつなのです。
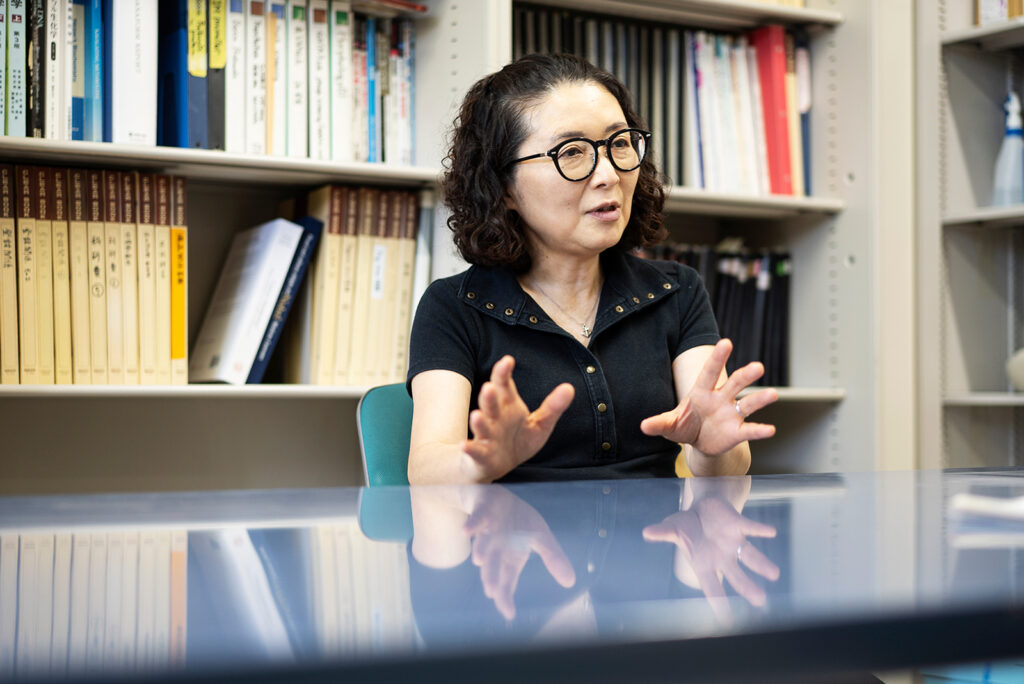
中心となるテーマは、老化に関わる酸化ストレス制御の仕組みである、と。
本橋
その通りです。外的な環境要因によって化学的な物質の曝露を受けたり、紫外線のような物理化学的な刺激を受けたりすることによって細胞はダメージを受けて変化するわけですが、私たちがいちばん知りたいのは、そうしたときに変化の触れ幅が極端な状態にならずにほどほどの範囲内に抑えられるような「恒常性維持」というものがいったいどういうメカニズムで実現されているのか、ということです。その研究の結果として、抗老化作用であったり、病気が少し良くなったり、ということが明らかになってきました。
そのNRF2という転写因子は私たちの体の中にふつうに存在していて、それが何かのきっかけで反応したり活性化したりする、ということでしょうか。
本橋
例えば、ブロッコリースプラウトの中に含まれているスルフォラファンという物質を食べるとNRF2は安定化し、働きはじめ、体を丈夫にするような遺伝子たちが活性化します。それにより、加齢に伴って増えてくる、細胞にとって好ましくないようなものが、あまり増えなくなります。つまり、変化があまり起こらない、という状態が実現されるのです。また、例えば、風邪薬のような、本来は体の中にない異物を体内に入れると、体はそれを外に出そうと解毒代謝します。その解毒代謝のために必要となるいくつかの酵素を統括的に制御しているのもNRF2です。
そこからの派生で、今は硫黄代謝の研究も進めています。硫黄というのもNRF2の下流で制御されている代謝で、NRF2が働くと新しい硫黄代謝物が増えるのです。これは硫黄原子を複数持つ物質で、生体内に存在することが近年ようやく確認されたため、「新しい」硫黄代謝物と呼んでいます。私たちは「超硫黄分子(スーパースルフィド)」5と呼んで研究を進めているのですが、抗酸化機能も抗炎症作用もとても強く、健康に良いことが期待されています。マウスが歳を取るとこうした硫黄代謝物が減ってくることや、硫黄代謝物が減ったマウスは早く老化することもわかってきました。
こういうメカニズムがわかることにより、ヒトにおいても、どうやって加齢を遅らせるか、どうやって健康な状態のままで歳を取るか、ということにつながっていくと考えています。
健康寿命を延ばす可能性が広がる、というわけですね。
本橋
そうです。私たちの研究の根幹にある想いとして、最終的にはヘルシー・エイジングに貢献できたら、というものがあります。それは直接的なものとしてではなく、とても基礎的なところ、分子メカニズムの解明というところで貢献したい、ということです。実際、仕組みとしてなにかがわかったとしても、それが実際本当にヒトに適用できるかどうかの道のりはかなり長いものになるものですから、その橋渡し的な役割はまた別のどなたかにお願いできれば…、ということになるかと思います。
また、これは研究とは離れた話になりますが、ヘルシー・エイジングのためには、「聞こえ」が非常に大事であることは個人的に非常に強く感じています。というのも最近は「難聴がアルツハイマーのひとつのリスク要因」と言われますし、それに関わる私の家族の経験があるから、です。
母とふたりで暮らしていた私の父は、歳を重ねて加齢性難聴になり、ふたりの会話は全く成立しなくなりました。すると、やがて母のほうが認知症を発症し、徘徊などするようになったのです。その後、父が亡くなって、それからは私が認知症の母と一緒に住むようになりました。日々、会話したり、ぎゅっとハグしたり、笑わせたり…ということをしているうちに、母の認知症の周辺症状がなくなり、徘徊することも感情の起伏が出ることもないほどに改善したのです。そんな経験から、「耳が聞こえて、話せて、コミュニケーションできて、触れ合う」というようなヒューマン・インタラクションが非常に大事なのだと痛感したのです。
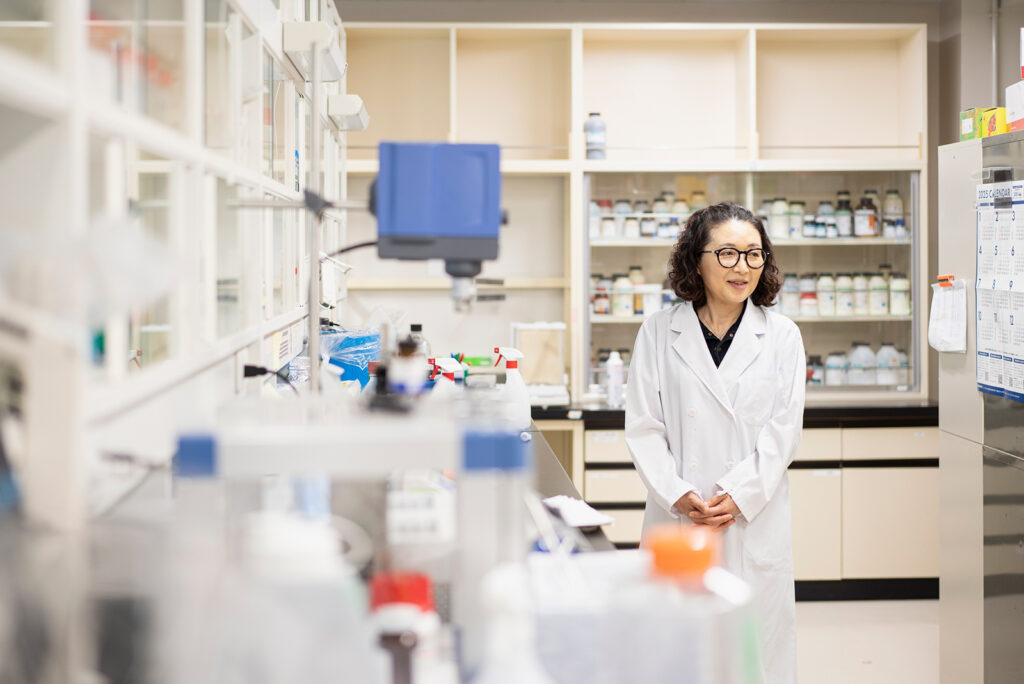
一方では酸化ストレス制御のメカニズムというお話もあれば、一方ではヒューマン・インタラクションの話もあり。抗老化といってもさまざまなレベルやアプローチがあり得るわけですね。
本橋
そうですね。たとえば、ふだんの生活の中でNRF2を活性化させる物質を取り入れていこうということを考えることもできるでしょう。そうしたときに鍵になるのは食品だろうと想像しています。というのも、老化というのはなにか極端な症状が出るものでもありませんし、長期間にわたるものですし。その予防的なものということになれば、薬ではないだろうと思うのです。食品とか、あるいは漢方あたりが近いのかな、と。私たちのサイエンスとはちょっと方向性が違いますけど……。
実際のところ、NRF2を活性化させる物質が入っている食品は、すごく強い作用があるわけではないかわりに、長い期間飲んでも副作用が少なく、ある程度の期待された効果は出ている、ということが検証されていますし、論文もあります。ですから、そういう食品やサプリメントの合わせ技がいいだろうと思います。
健康寿命を長くしたいと望む私たちに、日頃から心がけたいことなど、なにかアドバイスをお願いできますか。
本橋
先ほど、薬ではなく「食品」が良い、ということを申し上げました。ふだんの生活の中では、特に野菜を摂るのがいいでしょう。野菜は、動物では作り出せないようなさまざまな有用物質を生み出す力を持っています。さきほどお話した超硫黄分子も、タマネギ、ニンニク、ネギ、ブロッコリースプラウトなどの野菜に入っていますから、そういう野菜をふだんから積極的に摂っていただくこと。それがヘルシー・エイジングのためにはすごくいいことだろうと思いますね。
- (転写制御)遺伝子の情報をRNAに写し取る「転写」を調節する仕組みのこと。これにより、細胞は必要な遺伝子を必要な時に発現させ、様々な細胞機能や組織の分化を制御している。この転写制御において中心的な役割を果たすのが転写因子と呼ばれるタンパク質である。 ↩︎
- (山本雅之)東北メディカル・メガバンク機構長、東北大学医学系研究科 教授(医化学分野)https://www.megabank.tohoku.ac.jp/tommo/greeting ↩︎
- (東北大学加齢医学研究所) ミッションは、生命の誕生から発達、成熟、老化、死に至る加齢の基本的メカニズムを解明すること。得られた研究成果を応用して、加齢に伴う認知症などの脳・神経疾患や難治がんなどの克服を目指し、先端的予防・診断・治療法や革新的医療機器の開発を行う。https://www.idac.tohoku.ac.jp/site_ja/ ↩︎
- (香取幸夫)東北大学大学院耳鼻咽頭・頭頸部外科教授。 https://www.life.med.tohoku.ac.jp/features/32686/ ↩︎
- (超硫黄分子)「近年、硫黄代謝物の新しい定性・定量技術が開発されたことを端緒に、直鎖状に連結した硫黄原子(超硫黄/スーパースルフィド Supersulfide)を含む多様な硫黄代謝物が生体内に豊富に存在していることが明らかになりました。低分子の代謝物に含まれる超硫黄は、抗酸化作用や抗炎症作用を持つとともに、ミトコンドリアにおけるエネルギー代謝において必須の役割を担うことがわかってきました。すなわち、超硫黄分子は普遍的で必須の生命素子といえます。また、タンパク質のシステイン側鎖にも多くの超硫黄が含まれており、タンパク質の品質管理やシグナル伝達に関わることが明らかになってきました。」(「新興硫黄生物学が拓く生命原理変革~硫黄生物学~」https://supersulfide-proj.com/gaiyou.html より) ↩︎

本橋 ほづみ(もとはし ほづみ)
鹿児島市生まれ。仙台育ち。1990年に東北大学医学部卒業。耳鼻咽喉科での初期研修の後、1992年に東北大学大学院医学研究科博士課程進学。転写制御の面白さに魅せられて基礎医学に転向し、1996年に博士課程終了後、筑波大学先端学際領域研究センター助手に着任。2000年に8ヶ月の米国留学を挟んで、筑波大学基礎医学系講師、2007年から東北大学大学院医学系研究科准教授、2013年に東北大学加齢医学研究所教授、2023年から現職。現在の専門は、生化学・分子生物学。生体のレドックス制御を通して健康長寿に貢献したいと考えている。
Text:空豆みきお
Photo:三浦晴子













