
都市の水の安全なありかたと、ヒトの健康と、そして次の未来と。
佐野大輔(東北大学大学院工学研究科 下水情報研究センター センター長)
2025.8.1 Fri
新型コロナウイルスの感染拡大にまだ世界中がざわめいていた2021年。仙台市では「下水調査をもとに1週間先の新型コロナ陽性者数を予測する」という世界でも類を見ない試みがはじまっていました。そのプロジェクトにおいて中心的役割を担っていたのが、東北大学大学院工学研究科 下水情報研究センター センター長の佐野大輔教授の研究グループです。
都市の地下を流れる下水道の水という、医療の現場とは遠くかけ離れたような場所から得られたウイルスのデータをもとにして、地上に広がる感染状況の未来予測をするというその独自の取り組みはいかにして生まれたのでしょうか。
都市の水と健康との関わり、世代を超えて繋いでいくべきことについて、佐野教授にお話を伺います。
下水調査からコロナ感染者数を予測するという、世界的にも稀なその取り組みの経緯を教えてください。
佐野
そもそもは、下水中に排出されるノロウイルスの濃度をモニタリングすることにより感染性胃腸炎の流行を検知し、社会に情報を発信するシステムを構築するということに、私の恩師である大村達夫教授1が長く取り組まれてきました。大事な取り組みと思い、引き継いで継続しているうちにコロナ禍がはじまったので、ノロウイルスで培ったそのやり方を新型コロナウイルスに応用した、ということです。
重症化した感染者の情報は病院のほうに集まりますが、下水のほうには病院に行くことのない無自覚の感染者の排泄物に含まれるウイルスの情報も集まってきますから、そのぶんだけ幅広いデータを見ることができます。ただし、重症化をもたらさないウイルスの情報にいったいどれほどの重要性があるのか、という指摘は当然あるでしょうし、それについてはすでに議論もされてきました。
下水を調査して「ウイルスを見つけたぞ」と言ってみたところでそれほど意味があるものでもなく、下水中のウイルスのモニタリングに意義があるとするとそれは予測だろう、と私は考えています。ウイルス濃度や他の様々なデータを用いて予測モデルをつくり、AIによる機械学習によって1週間先の未来の感染状況を予測をする。そして、メールやホームページで情報発信することによって、人々への注意喚起を促す。それが、予防意識を高めてもらうことや行動を控えてもらうことの働きかけとなって、感染流行の抑制につながるということだろう、と。
振り返ってみますと、コロナ禍がはじまったばかりの最初の頃は、そもそも新型コロナウイルスが下水中に排出されるかどうかもわからない、というところからのスタートでした。やがて排出されることがわかって、調査してみると、今度は濃度が非常に低いという問題にぶつかりました。下水中からウイルス遺伝子を回収するために、ウイルス特性に応じた新しい方法を見つけ出さなければならないことがわかって、下水中の新型コロナウイルスを効率的に集める濃縮法を確立させたことによって、モニタリングできるようになったのです。
コロナ禍がおおよそ収束した現在ですが、私たちの研究室ではノロウイルスに関しての感染予測を行う準備をしています。最近では、新型コロナウイルス感染症予測の時よりもさらに長期の、1カ月先の感染者数を予測することを試みています。それによって、患者を受け入れる病院側の準備や検査機関の試薬の備蓄など、感染症対応の体制強化に役立ててもらえるのではないかと考えています。

都市の上下水道とそこに生きる人々の健康な暮らしは、密接に関っているのですね。
佐野
私たちの研究室は「環境水質工学研究室」というのですが、その前身は「水道研究室」という名前でした。水道の水というのはヒトの口に入るものであり、ヒトの健康に直接関わってくるものですから、ウイルスはもちろん、微生物や化学物質や重金属など、昔から実にさまざまな研究がされてきました。最近よく耳にするPFASなどもそうです。
上下水道システムでは、使うときには水をきれいにして使わなければいけないし、使った水はまたきれいにして環境に戻さなければなりません。この「水をきれいにする」ことはどうしても不可欠なことですし、それに加えて、この水道システム全体をいかにして将来に向けて持続可能なものにしていくかが重要となってきています。
先日とある町で水道管が破裂したというニュースがありましたが、こうしたことは日本各地で起きています。社会インフラの寿命は50年くらいの想定であり、古くなったり錆びてきていたり、すでに寿命を迎えている水道管は少なくありません。本来ならこれら全てを新しいものに入れ替えなければなりませんが、それには莫大なコストがかかります。そうした状況の中でいかに対処できるかが課題なのです。 仙台市の水道局でも、水道管の劣化状況の把握が進められています。古くても使える管はそのままに、まずは危険度の高い箇所を特定して優先的に入れ替えていくことが求められています。下水道管でも状況は同じであり、都市の地下に張り巡らされた上下水道管のうちどこがどの程度劣化しているかを見極めることが重要です。
その上下水道管を入れた時期はいつか。交通量はどうか。たとえば、ダンプカーが多く通行する道路の下は強い振動によって劣化が早くなります。また、場所はどうか。たとえば、海に近いと塩で錆びやすくなります。そして、材質はどうか。コンクリートなのかプラスチック系なのか……。劣化に関わるそうしたデータをもとにした機械学習によって「ここが危険かも」という予測が可能になります。こうした上下水道管の劣化予測にも、私たちの研究室で取り組んでいます。 また昨年は、40箇所のマンホールを開けて、下水管の水の調査を行いました。卵の腐ったような匂いを発する硫化水素がコンクリート製の下水管を劣化させるのですが、硫化水素をつくるバクテリアの下水中の量を測ることによって、危険度が高いと想定されるポイントをマッピングしていく、というような取り組みです。

都市に安全安心な水があるのは当たり前だと私たちは思っていますが、それは上下水道の仕組みや、水質調査による危険の事前察知や改善によって支えられているわけですね。
佐野
「水道が使えなくなる」とか、「下水が使えなくなる」という状況を、ふだん私たちは想像すらしないものですが、しかし、水道システム全体を見渡してみたとき、将来に向けてそれほど安泰ではない、という危機感を持っています。
水循環システムをどうやって持続可能なものにしていけるのか、今あるレベルをどうやって維持できるのか、というのは非常に重要なテーマです。場合によっては、処理レベルを下げなければいけない、下げざるをえない、などということが起こりうるわけで、そうならないようにしていかなければなりません。病気になる確率が一定以下に抑えられている水質のレベルの高さはこれからも維持されなければなりませんし、そうしたことに支えられている都市の安心な暮らしの恩恵というものを、子どもやその先の子孫へと世代を超えてしっかりと繋げていくということが、今を生きる私たちの世代の責任だろうと思います。
今回のこのLIFEマガジンの特集テーマは「水」です。「水と〈いのち〉」という言葉からどんなことをイメージするか、お聞かせください。
佐野
災害が起きたときに人々が意識するもの、でしょうか。
今は気候変動によって雨の降りかたが大きく変化していますし、雨量も増えていますから、想定していなかった状況が生じやすくなっています。ここで重要になるのは水の「量」をきちんとコントロールできるか、です。量が管理できなければ、川が溢れて洪水になるとか、下水管から水が溢れてしまうといった大変な事態となります。ヒトのいのちや財産が危険にさらされますし、ときには失われてしまいます。
災害となれば、私たちは避難所生活を送らなければならなくなり、そうなると水の「質」の問題が浮かび上がってきます。飲み水や下水をしっかりしないと衛生環境が悪化してしまいます。日常生活とはまた別の、そういった非常時の水の「質」をどう確保できるのか、ということですね。また、洪水が起きた場合には、流木などによって水道橋が破壊される事態が起きやすくなることも念頭に入れなければなりません。もしそうなれば断水になりますし、しかも長期間にわたるでしょう。水の手段が他になければ危機的な状況を招くことになります。
大きな病院の多くは、そういった場合にも医療行為がストップすることのないよう、地下水利用のシステムを備えています。こうした備えが重要であることは、私たちの日常生活においても同じです。川やダムの水を使うだけではなく、地下水も利用できるような備えをしておいて、その両方をうまくバランスをとりながら運用していくということが、将来的に必要になってくるのではないでしょうか。

この先の未来のために、これから考えていくべき課題として、どんなことがありますか。
佐野
下水処理で「水をきれいにする」とき、微生物に下水の汚れを食べてもらうやり方をしています。この方法は活性汚泥法と呼ばれています。活性汚泥というのは、いわば微生物の集合体です。
その活性汚泥はこれまで、使われたあとは産業廃棄物として焼却され、最終処理場に廃棄されてきました。それが最近では、活性汚泥の主成分が有機物であり肥料にもなりうることから、再利用すべきだという流れになっています。特に注目されているのがリンです。汚泥には肥料の主要成分であるリンが豊富に含まれているため、このリンを回収し肥料として再利用することで、現在輸入に頼っているリンを国内で循環できるようになるなどのメリットが期待されています。しかし、それを現実にやっていこうとすれば、考えるべき点がいろいろあります。
たとえば、現在の下水というのは、家庭から流れ出た後、最終的には遠く海沿いなどの処理場まで運ばれて処理されていますが、汚泥を再利用して肥料として使うことを想定すると、処理場をもっと上流に移し、田畑の近くに配置する必要があるのではないか、ということになってくるでしょう。つまり、下水処理場が都市に暮らす人たちにとって今よりももっと身近なものになってくるわけで、そのことがもたらす人々の健康への影響を考慮しなければなりません。健康リスクが悪化しないためには、どうすればいいのか。私たちの研究室では、こういうシステムならいいのではないかという計算や、それを実際にどう実現できるのかという課題に取り組んでいるところです。
都市の水循環システムというものも、時代の要請に応じて少しずつ変わりゆくわけですが、そうしたなかでも都市の人々の健康を支える水の安全はしっかりと守られなければなりません。そこに潜む危険性を察知することやリスクを減らすことによってその安全性を支えていくということ。それが、私たちの仕事だと考えています。
Text:空豆みきお(akaoni)
Photo:三浦晴子
- (大村達夫)東北大学 未来科学技術共同研究センター 名誉教授 ↩︎
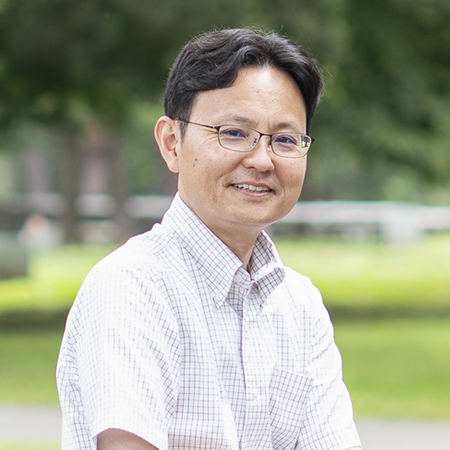
佐野 大輔(さの だいすけ)
2003年 東北大学大学院工学研究科土木工学専攻博士後期課程修了。博士(工学)。同年 日本学術振興会特別研究員(PD)、2007年 日本学術振興会海外特別研究員(バルセロナ大学生物学部微生物学科)、2009年 北海道大学准教授、2015年 バルセロナ大学客員准教授(兼務)などを経て、2017年 東北大学大学院工学研究科土木工学専攻准教授、2018年 同大学院環境科学研究科准教授、2021年4月 現職。2022年12月 東北大学工学研究科下水情報研究センター長就任。2008年 文部科学大臣表彰若手科学者賞など受賞歴多数。













