
マイノリティの想いを「きく」
五十嵐大
2025.5.21 Wed
耳の聴こえない両親を持つ、コーダとして生まれ育った五十嵐大さんは、自身の生い立ちによるエッセイ、社会的マイノリティへの取材を中心に、今までたくさんの方々のお話をきいてこられました。そんな五十嵐さんにとっての「きく」とはどういうことなのか、取材中でのエピソードをもとに、ご寄稿いただきました。
マイノリティの想いを「きく」
仕事柄、誰かの話をきく機会が多い。その際、心がけていることがある。余計な先入観や思い込みを捨て、純粋な疑問をぶつける、ということだ。もちろん、相手の心にズケズケと土足で踏み込むということではない。敬意を払いながらも様子をうかがい、わからないことや疑問に思ったことは素直にきくのだ。
これはときに、怖いことでもある。たとえば、相手の逆鱗に触れる可能性もあるし、意図せず傷つけてしまうリスクも孕んでいる。それでも、「きく」ことからすべてがはじまると思っている。
こう考えるようになった出来事がある。
ライターとして、難病児を育てる親御さんにインタビューしたときのことだった。その子は車椅子に乗っていて、自ら体を動かすことも困難な病気だった。笑いかければ少しだけ表情を崩してくれるものの、しかし、いまどんな気持ちでいるのか、身内ではないぼくが読み取るのは難しい。親御さんの話だと、長く生きることは難しいという。
そんな前提を理解したうえでのインタビューだったので、ぼくは質問することに臆してしまった。どこまできいていいのだろう……。親御さんを傷つけないように、と考えすぎる余り、質問が出てこない。それでもなんとかインタビューを終えると、親御さんが静かに口を開いた。
「こないだ、嬉しいことがあったんです」
「どんなことですか?」
「同じマンションに住んでいる小さな子が、うちの子を見て、『ねぇ、どうしてこの子は車椅子に乗ってるの?』ってきいてくれたんですよ」
大人だったら、絶対にきかない質問だろう、と思った。そんな質問をされたら、親御さんがどれだけ傷つくだろうかと想像するからだ。しかし、ぼくのそんな考えを根底から覆すようなことを、その親御さんは言った。
「それが本当に嬉しかったんです」
「え?……どうしてですか?」
「このマンションに住んでいる大人はみんな、私たちに遠慮して、話しかけてこないんです。可哀想だから、と思っているのかもしれません。だから、気になることを率直にきいてくれたことが嬉しかった。私たちを透明人間にはせず、そこにいる人として扱って、質問してくれた。それが嬉しかったんです」
マンションに住む大人たちがしていたのは「配慮」だったのかもしれない。難病児を育てる人を不必要に傷つけないための「やさしさ」だったのかもしれない。ただし、それが親御さんを透明人間にし、そこにいないものとし、結果として傷つけてしまった。
でも、その親御さんが求めていたのは、素直に「きいて」もらうことだった。
「きく」という行為は、相手の存在を認めることだ。その存在を目の前に認め、知りたいという意思を伝え、同じ世界に生きる人同士、手を繋ぐことだ。それがどんなにありがたいことなのか、ときに排除されてしまう側にいる親御さんの言葉から、ぼくは学んだ。だから、まずは相手の話を「きく」ことを大切にするようになった。その相手がマイノリティであればなおさら、現代社会のなかでどんな困りごとを抱えているのか、あるいはどんなときに幸福を感じるのか知るために、心を寄せる。そうすることで、いままで見えていなかったことが見えてくるから。相手の存在を、ただただ尊重することができるから。

耳の聴こえない両親から生まれたコーダであるぼくには、ろう者や難聴者の友人が多い。彼らのなかには、「生まれ変わっても聴こえないままでいい」と話す人も少なくない。その理由は「聴者にはなりたくない」「ろう者であることに不便を感じていない」「いまの人生が楽しいから」「手話で生きることに誇りを持っている」など、実にさまざまだ
彼ら彼女らのようなろう者、難聴者と接点がない聴者からすれば不思議に思うかもしれない。なかには、「ろう者、難聴者はみんな、聴こえるようになりたいと思っているに違いない」と考える人もいるだろう。でも、それは違う。彼ら彼女らは独自の「ろう文化」を大切にし、聴こえない自分に誇りを持って生きている。
ろうや難聴の子どもが生まれたとき、聴者の親は医師に勧められるまま人工内耳手術をすることがあるという。それによって少しでも聴者に近づければ、と願うのだろう。その苦しい胸中を想像すると、納得する部分もある。でも、人工内耳だって完璧ではない。ろうや難聴で生まれた人が、手術によって聴者と同じになれるわけではない。それでも手術を決断する親が絶えないのは、聴者に合わせなければいけないという思い込みに囚われているからではないか。
そういった聴者側の思い込みや偏見が、ろう者や難聴者を追い詰めることにつながる。だからこそ、「きく」ことを大切にしなければいけない。「あなたが本当に求めているものはなんですか?」と。
それは他のマイノリティにも言えることだと思う。目が見えない、うまく歩けない、手を動かせない……、さまざまなマイノリティの人たちを前にしたときに「この人たちは障害をなくしたいはずだ」「どうすれば治せるのか」と考えるよりも、まずは彼ら彼女らがそのままの状態で不自由なく生きていくためには、なにが必要なのかを「きく」こと。そこで知ったことを社会に実装するためにどうすればいいのかと心を砕くこと。それこそが、あらゆる人と共生していく社会の実現を叶える、第一歩なのだと思う。
ぼくはこれからも、マイノリティの想いを「きく」ことを、大切にしていきたい。
Illustration: 河野愛
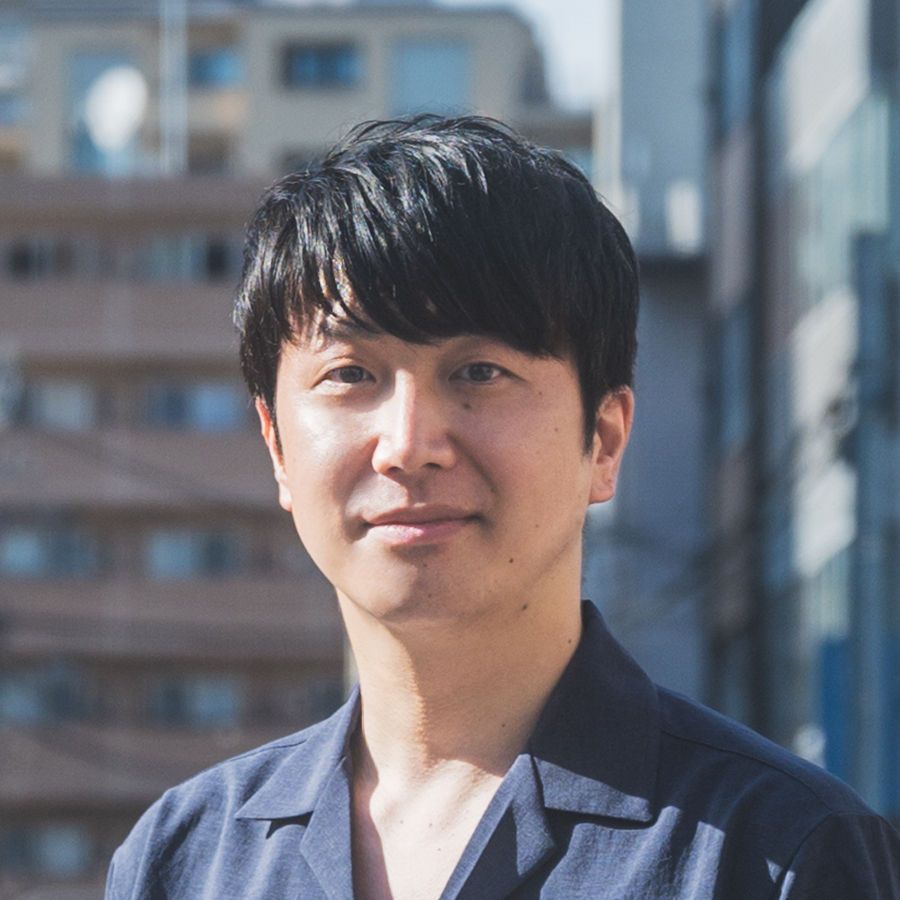
五十嵐大
Dai Igarashi
1983年、宮城県塩竈市生まれ。耳のきこえない両親を持つ、コーダとして生まれ育つ。2020年、『しくじり家族』(CCCメディアハウス)でエッセイストとして、2022年、『エフィラは泳ぎ出せない』(東京創元社)で小説家としてデビュー。2024年9月、『ろうの両親から生まれたぼくが聴こえる世界と聴こえない世界を行き来して考えた30のこと』(その後、『ぼくが生きてる、ふたつの世界』と改題し文庫化)を原作とした実写映画「ぼくが生きてる、ふたつの世界」が公開される。その他の著書に『聴こえない母に訊きにいく』(柏書房、2023年)、『「コーダ」のぼくが見る世界』(紀伊國屋書店、2024年)など。
(写真:島津美紗)













