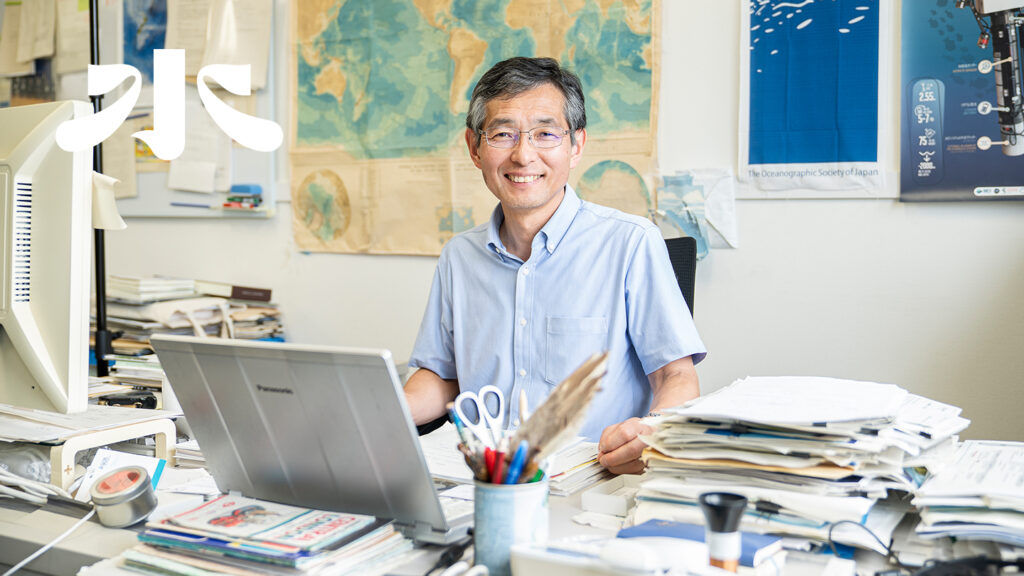
海洋生態系という「いのち」をめぐって(1)
─ 海を観測する ─
須賀利雄(WPI-AIMEC所長・東北大学大学院理学研究科 教授)
2025.8.29 Fri
2024年に東北大学と海洋研究開発機構(JAMSTEC:ジャムステック)が共同で設立した「変動海洋エコシステム高等研究所」(以下、WPI1-AIMEC:ダブリューピーアイエイメック)は、海洋に存在する⽣態系に焦点をあて、学際的なアプローチにより、海洋⽣態系の維持に重要な連動性・安定性・適応性の理解を深化させ、人間社会に役立つ、海洋⽣態系の変動予測の実現を目指す研究所です。
地球の表面の約7割は海が占めていることからもわかる通り、海を理解することは、地球の環境はもとより、私たち人間、そしてあらゆる生命(いのち)を理解することと、ニアリーイコールなのかもしれません。
今回は、WPI-AIMEC所長の須賀利雄先生に、研究所の活動内容を軸に、まだまだ謎の多い海の観測についてお話しいただきました。
まずは、WPI-AIMECの活動内容についてお教えください。
須賀
地球温暖化をはじめとする地球環境の急激な変化が現在進行形で進んでいるのはご存知のとおりかと思います。私たちは、そうした地球環境の変化に対して、海の生態系がどのように応答するのか、そのメカニズムを理解すべく活動しています。地球の環境変化に海が「応答する」「適応する」というプロセスを解明し、その知見を海の将来を予測するモデルへと活用していくことがWPI-AIMECの目的です。
気候変動に限らず、より小さなスケールでの様々な環境変化に対しても生態系がどう応答/適応するのかを把握した上で、数値予報モデル2にその知見を組み込んで精度を高めていきます。そうすることで、将来の海洋生態系の変動をより正確に予測し、有益な情報として私たちの社会へと還元していくことができるのです。
海は、地球環境の維持において非常に重要な役割を果たしています。変化が進みつつあるものの、現在の地球環境は、私たち人間にとって生存に適した状態の範囲内にあるといえます。この状態をなるべく持続させていくことが、私たち人類にとって望ましいことでしょう。一方で、人間が地球に対してできることには限りがあります。それでも、海ひいては地球の持続可能性に資するような知見を社会に提供していくことがわれわれの使命だと考えます。
私たちはこのような考えや取り組みのことを「惑星スチュワードシップ」(Planetary Stewardship/地球の持続可能な管理と保護のための責任ある行動規範・原則)と呼んでいます。もちろん、「人間が地球環境を完全にコントロールできる」と考えるのは過信ですが、産業革命以降の人間活動が現在の気候変動を引き起こしているのも事実ではないでしょうか。だからこそ、私たち人間の活動のあり方を見直し、環境への影響を少しでも軽減する方向へと調整していくことが求められているのです。
地球環境の変化が著しくなってきている今だからこそ、その先で少しでも良好な状態を保てるよう、人間として何ができるのかを考えていく必要があります。私たちは、そうした問いに対して有効な知見を基礎研究から導き出し、提供していきたいと考えているのです。
海の研究というのは、現在どの程度まで進んでいるのでしょうか。まだ知られていない事象も多いのでしょうか?
須賀
海の研究というのは、実は非常に古くから行われてきました。近代的な観測や理論研究に限っても、もう100年、あるいは、それ以上前から取り組まれています。もともとは、地球としての海というよりは、私たちの身近な海としての研究が中心でした。人間の暮らしと密接に関わっていた浜辺や沿岸部での観察や知見は、研究という形式を取らずとも、昔から蓄積されてきたわけです。
ただ、地球儀を見れば分かる通り、海はすべてつながっています。私たちは最近「One Ocean」(ワン・オーシャン)という言葉をよく使いますが、そうした「地球規模での海」をどれだけ理解できているかというと、実はまだまだ不十分なのが現状です。というのも、広大な海は私たちの日常生活からは遠い存在で、特に遠洋については、かつては資料も観測手段も極めて限られていたのです。
転機となったのが人工衛星の登場です。これによって、少なくとも海の表面に関しては、温度や海の色(さまざまな波長の太陽光の反射から得られる情報)、さらにはレーダーを使った海面の高さの測定などが可能になりました。センチメートル単位の精度で、海面の高さを測ることで、表層循環も把握できるようになってきたのです。
海面の水温の観測は1980年代から、海面の高さ(海面高度)の測定は1990年代から本格化し、こうした衛星データのおかげで、地球規模での海の表面付近の様子が捉えられるようになりました。
しかし、問題は「海の中」です。電波は水中を通らないため、リモートセンシングでは測れません。音波を使う方法もありますが、それには限界があります。そのため、海の内部を精密に観測するには、今もなお船を使って観測装置を海中に下ろすという、伝統的な方法が主流なのです。
象徴的な例として、月の地形の方が海底地形よりも詳しく観測されている、という事実があります。海の深さを正確に測るには、狭い範囲に音波を絞って計測する必要があり、精密なデータを得るには、海をくまなく船で走り回らなければなりません。現実的には、それは極めて困難です。
つい10年ほど前までは、海底地形の詳細なデータのカバー率は6%ほどでした。近年では、日本財団が支援する国際プロジェクトによって、ようやくそのカバレッジが広がりつつあります。それでも、海底地形の詳細像はまだ十分に分かっていないというのが実情です。
海の地形だけでなく、海水の循環についても、この50〜100年でおおよその様子が分かってきました。しかし、詳しい内部構造まではなかなか把握できていませんでした。そこで登場したのが、自動観測ロボット観測網「アルゴ」(Argo)3です。私もこのプロジェクトに関わっていますが、アルゴによって、空間的にも時間的にも万遍なく海を観測することが可能になってきました。
海の観測も、気象観測と同様に一度測れば終わりではありません。常に変化しているので、継続的な観測が必要です。しかし、世界中の海を海面から深海まで測り続けるなんて、船での観測しか手段がなかった時代には不可能でした。それを可能に近づけたのがアルゴです。現在、世界中の海に約4000台のアルゴ・フロート(自動観測ロボット)が展開されており、海水の重要な要素である「水温」や「塩分」を計測しています。この2つの要素で海水の「素性」がある程度わかるほか、海水の密度は温度と塩分によって決まるという点も重要です。
水温が低いほど、また塩分が高いほど、海水は重くなります。この密度の分布が分かると、海の中での水の「重さ」、そしてその結果として決まる「圧力」の分布が分かります。これは、大気でいう「天気図」のようなものを海の中に描けるということを意味します。つまり、海の中の循環構造が見えてくるわけです。
私は「海洋物理学」という、海を物理的に理解する分野を専門としていますが、水温と塩分は、この分野においてもっとも基本的なパラメーターです。アルゴの観測網によって、それを安定的に取得できるようになったことは、大きな前進です。
アルゴによる水温・塩分の継続的な観測は2000年頃に始まり、地球規模の観測網として整ったのは2007年頃。今では約4,000台の観測機が安定的に運用され、20年近くその記録が積み重ねられています。そして現在、そのアルゴをさらに拡張しようという動きが進んでいます。
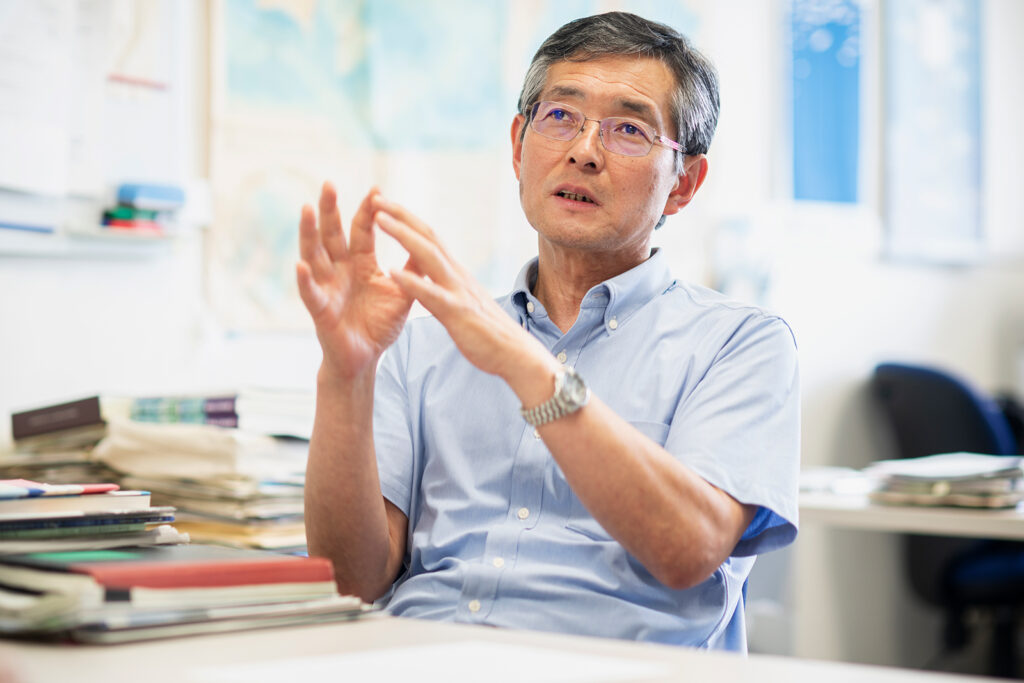
海の観測方法も日々進化しているということでしょうか。
須賀
当初のアルゴは水深2,000メートルまでの観測に対応していましたが、近年では水圧に耐える技術が向上し、水深6,000メートルまで測れる機器も開発されています。「海底まで観測しよう」という拡張がそのひとつです。
もうひとつの拡張が、観測項目の拡大です。従来の水温・塩分に加えて、たとえば海水に含まれる酸素(溶存酸素)、植物プランクトンの量を示すクロロフィル濃度なども、新たに測定できるようになってきています。
そして、植物プランクトンが光合成を行うために必要な栄養素、いわゆる「栄養塩」についても観測できるようになりました。中でも代表的なものが「硝酸塩」です。栄養塩は植物プランクトンの増殖を支える重要な物質です。太陽の光がどの程度の深さまで海中に届いているかという情報も非常に重要な観測項目となります。これは、光合成がどこまで可能かという生態系の基本に関わる指標であり、専用のセンサーを使って測定しています。
加えて、海中に存在する「粒子」も観測対象となります。たとえば、表層付近で植物プランクトンが光合成によって増殖し、それを動物プランクトンが捕食し、さらにそれを魚が食べるという食物連鎖の中で、死骸やフンなどの有機物が発生します。これらの粒子は海中を沈降していきます。
これらの粒子の観測には、光学的な手法を用います。具体的には、観測装置から光を照射し、それが粒子に当たって後方へ散乱される光(後方散乱)を測定することで、粒子の量や分布を把握することができます。
さらに、海の酸性化を示す「pH」も重要な観測項目です。近年ではpHを精密に測定できるセンサーも開発されており、私たちのチームでも昨年、こうしたセンサーを搭載した自動観測ロボット(フロート)を3台購入して、実際の観測に使用しています。
これらの観測装置の中には「アンダーウォーター・ビジョン・プロファイラー」(Underwater Vision Profiler)と呼ばれる最新の機器もあります。これは、海中で一定の時間間隔でフラッシュをたきながら、一定量の海水(およそ0.6リットル)中の粒子をカメラで撮影するものです。この撮影によって、その水の中にどんな粒子がどのくらいあるかを視覚的に記録します。撮影された画像はAIによって解析され、プランクトンの種別や粒子のサイズ分布などが特定されます。このプロファイラーは、フロートが水深2,000メートルから浮上する間ずっとデータを取得するため、深さごとの粒子の分布(縦方向のプロファイル)を詳細に記録できます。ここでいう「粒子」には、プランクトンなどの生物も含まれています。
このように、最新の観測技術を搭載した装置を、私たちは実際に海洋観測で使用しているのです。
Text:アイハラケンジ
Photo:三浦晴子
- WPI:文部科学省による「世界トップレベル研究拠点プログラム」のこと。第一線の研究者が世界から多数集まってくるような、優れた研究環境と高い研究水準を誇る研究拠点の形成を目指す事業。 ↩︎
- 数値予報モデル:地球大気や海洋、陸地の状態を支配する物理法則の数式をコンピューターで解き、将来の大気・海洋・陸面の状態を予測するシステム。世界から送られてくる観測データを基に、大気の状態などを格子状の点(格子点)で表現し、それぞれの点における気象要素や海洋や地面の温度などの値を計算することで、将来の気候を予測する。 ↩︎
- アルゴ計画:2000年にスタートした国際プロジェクト。「アルゴフロート」と呼ばれる海洋内部をモニタリングするロボットが、全世界の海に投入され(現在 約4,000台)、海面から深度2,000mまでの水温、塩分、圧力を10日間隔で計測している。 ↩︎
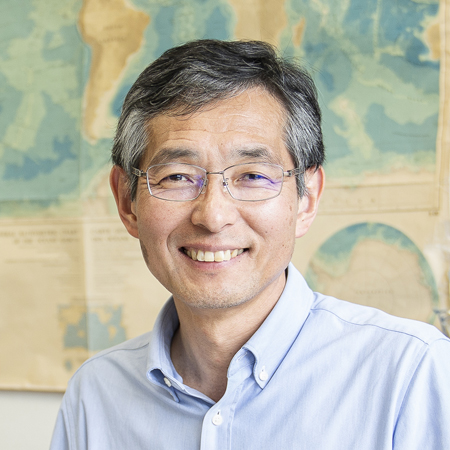
須賀 利雄(すが としお)
東北大学・海洋研究開発機構 変動海洋エコシステム高等研究所長、大学院理学研究科教授。海洋研究開発機構上席研究員を兼務。理学博士。主な研究分野は海洋物理学。国際アルゴ計画に開始時から参加し、アルゴ運営チームの共同議長も務めた。UNESCO/IOC「全球海洋観測システム」運営委員会コアメンバー、IPCC「海洋・雪氷圏特別報告書」代表執筆者などを歴任。













