
海洋生態系という「いのち」をめぐって(2)
─ WPI-AIMECが目指すこと ─
須賀利雄(WPI-AIMEC所長・東北大学大学院理学研究科 教授)
2025.9.5 Fri
2024年に東北大学と海洋研究開発機構(JAMSTEC:ジャムステック)が共同で設立した「変動海洋エコシステム高等研究所」(以下、WPI-AIMEC:ダブリューピーアイエイメック)は、海洋に存在する⽣態系に焦点をあて、学際的なアプローチにより、海洋⽣態系の維持に重要な連動性・安定性・適応性の理解を深化させ、人間社会に役立つ、海洋⽣態系の変動予測の実現を目指す研究所です。
地球の表面の約7割は海が占めていることからもわかる通り、海を理解することは、地球の環境はもとより、私たち人間、そしてあらゆる生命(いのち)を理解することと、ニアリーイコールなのかもしれません。
今回は、WPI-AIMEC所長の須賀利雄先生に、海洋生態系を研究することの意義から、WPI-AIMECが目指す方向性についてお話しいただきました。
やはりこの時代、海洋生態系の研究にもAIが積極的に活用されているのでしょうか。
須賀
最近では、AI(人工知能)・機械学習の技術が海洋研究にも積極的に導入されるようになってきました。膨大なデータが得られるようになった一方で、人間の頭脳だけではとても処理しきれないような状況にもなっています。特に、海洋環境や生物の分布、人間活動との関係性など、取り扱うテーマがますます広がりを見せる中で、AIに代表されるコンピュータの支援は今や不可欠です。
かつては「海にどんな生き物が、どこに、どれくらいいるのか」を知るには、実際に生物を採取して、目で見て数えるしかありませんでした。たとえばプランクトンや小型の生物を捕まえ、顕微鏡でひとつひとつ数えるという、非常に地道な作業をしていたわけです。ところが今では、環境中のDNA解析技術の進化によって、状況は一変しました。
たとえば、ある海域の海水を一定量 ―生物が豊富な沿岸部ではごく少量でも十分ですが、外洋などでは20リットル程度かそれ以上の海水を採取し、それをろ過して残った生物由来の微細な物質からDNAを抽出します。これによって、「どんな生き物が、どのくらいいたか」という情報を網羅的に把握できるのです。この技術は、海洋生物のサンプリングの方法として、まさに革命的といえるものでしょう。
加えて、先ほどお話ししたように、アルゴによる物理観測や化学的な成分の大量取得も進み、データ量は爆発的に増え続けています。こうしたデータは、もはや従来の人間の処理能力だけでは解析しきれません。だからこそ、AIを活用した新たな解析手法の開発が重要になってきています。私たちも、まさに今そうした取り組みに挑戦しようとしているところです。
そこで得た様々なデータは、どのように解析され活用されていくのでしょうか。
須賀
それこそが、私たちが現在取り組んでいる研究そのものです。まず、水温や塩分といった基本的な情報は、昔から船を使って測ってきました。それを用いて、海水の「重さ」、つまり密度を計算し、それを鉛直方向に積算することで、圧力の分布を求め、海の循環を理解しています。では、水温や塩分は何によって決まるのか。それは、海の表面で決まります。たとえば、海面が冷やされると水温が下がり、蒸発が進むと塩分は上がり、逆に雨が降れば塩分は下がります。こうした変化が起こるのは海の表面だけです。そして、表面で特徴づけられた水は、そのまま表層にとどまるものもありますが、一部は沈み込み、深い海へと運ばれていきます。世界中の深海にある海水も、もとはどこか別の海域の海面で生まれたものなのです。
例えば、太平洋の水深5,000メートルの海水も、その起源をたどると、大西洋北部や南極周辺で生成された水が混ざり合ってできたものだと考えられます。水温や塩分の分布を手がかりに、水が「どこで生まれ、どのような経路を通ってきたか」や、「海面を離れてからどのくらい時間が経っているのか」などが、ある程度推定できるのです。
さらに、栄養塩や溶存酸素といった情報を組み合わせることで、これらの推定がより正確になります。私たち海洋物理学の立場からすると、海水の三次元的な分布、それがどこで形成され、どのように移動してきたかを明らかにすることが、非常に重要なポイントの1つなのです。
物理的な水の分布や流れを理解することは、それが舞台となって、植物プランクトンの光合成や、それを食べる動物プランクトン、さらには魚類などの生態系がどのように成立しているのか、さらに、それらの生物が排出した有機物が、バクテリアによって分解される「リミネラリゼーション」(鉱化作用)を経て、再び栄養塩となってどのように海の中を循環しているのかなどの全体像を理解するための基礎となるのです。
このように、生物の活動は、物理的に整えられた海洋環境の上で成り立っているといえます。
ただし、実際には生き物もまた、その物理環境に影響を与えているのです。たとえば、海を温める主な要因は太陽光ですが、その光は深くまでは届きません。通常、太陽光は水深100メートルほどでほぼ減衰し、それより深い層には届きません。
植物プランクトンは光合成をするので太陽光を吸収するため海面近くに存在します。そのため、プランクトンが多い海域では、光がプランクトンによって遮られ、海中深くまで届かず、海を温める層が浅くなります。一方で、プランクトンが少ない海域では、光がより深くまで届き、海のより深い層まで温められるのです。つまり、生物の存在が海の温度構造に影響を与えているのです。
また、海には黒潮のようなはっきりした海流だけでなく、センチメートルのスケールから1万キロのスケールまで、さまざまなスケールの循環や流れがあります。これらが熱や物質、そして栄養塩を運んでいます。
特に、植物プランクトンにとって必要な栄養塩(窒素・リン・ケイ素)は、表層にはあまり残っていません。なぜなら、光が届く浅い層では光合成が活発に行われ、栄養塩が消費されてしまうからです。やがて有機物は沈降し、深海でバクテリアによって分解され、再び栄養塩に戻ります。そのため、逆に深海には栄養塩が豊富にあるのです。
これらを再び表層に運ぶのが、海の循環や混合といった物理的プロセスです。つまり、植物プランクトンが安定的に生き続けられるのは、こうした循環があるからなのです。そして、循環が変われば、植物プランクトンの分布や活動も大きく変わってしまうといえます。植物プランクトンが変化すれば、それを食べる動物プランクトンや魚類も変化し、海の生態系全体に波及します。つまり、海の「基礎生産」(一次生産)である植物プランクトンの光合成、ひいては海の生態系は、物理的な環境に強く依存しているのです。

海の中も陸上と同じように物理的な環境が存在し、そして複雑な生態系が存在しているのですね。
須賀
海の光合成量は、陸上の植物による光合成量とほぼ同じであるという点はご存知でしたでしょうか。つまりこれは、地球上の光合成の半分は、海の中で行われているということなのです。海洋生態系がもし機能しなくなれば、酸素の生産量が落ち、大気の成分にまで影響を与える可能性もあります。そもそも現在の地球大気に酸素が豊富にあるのも、過去に海のプランクトンが酸素をつくってきたからともいえます。
現在でも、海の植物プランクトンが大量の光合成を行っているおかげで、地球環境が維持されているのです。ですから、これは「海の話」で終わるものではなく、私たちの生活環境そのものに深く関わっている話なのです。
ところが現在、温暖化によって海水温が上昇し、さらには海が二酸化炭素を吸収することで酸性化も進んでいます。厳密には酸性にはなっていませんが、弱アルカリ性だった海水が中性に近づいているのです。そうなると、炭酸カルシウムの殻を持つプランクトンなどの微生物が生存できなくなる可能性が出てきます。これが進行すれば、生態系の土台が崩れ、環境に甚大な影響が及ぶことになります。そうした現象を、海水温の変化・酸性化・酸素供給の減少といった要因から、根本的に理解したい。それが私たちWPI-AIMECが目指しているところなのです。
海洋生態系の根本的な理解には、生き物の分子レベルの応答から、地球規模の気候パターンまでを結びつけて理解する必要があります。これまでも、それぞれ個別の研究は進められてきましたが、それらを統合し全体像として理解する試みはほとんど行われてきませんでした。なぜなら、私たちのような海の循環を専門とする物理系の研究者にとって、生き物の分子レベルの応答やRNAの変化は専門外であり、手が届きません。同様に、生物学の研究者も物理的な循環や混合の知見には詳しくありません。
こうした「分野の断絶」が、統合的な理解を阻んできました。ですから、分野の異なる研究者が同じ屋根の下で、日常的に疑問や気づきを共有できるような研究環境 ―アンダーワンルーフ(Under One Roof)の場が必要だと考え、この研究所が設立されたのです。
これは非常にチャレンジングな試みです。一朝一夕でできることではありませんが、今、私たちは分野の違う研究者同士で、毎週オンラインでセミナーやディスカッションを重ねています。また、月に2回は「AIMEC Café」と呼ばれる雑談の時間も設け、さらに2カ月に一度は対面でのコロキウムも行っています。3年後には、新青葉山キャンパスに新しい研究棟が完成する予定ですが、それまでの間はオンライン環境を活用しながら活動を続けていきます。
そしてもう一つ。AIMECは東北大学だけで運営しているわけではありません。海洋研究開発機構(JAMSTEC)との共同運営となっており、私たち東北大学側の研究者と、JAMSTECの研究者が相互に兼務する体制が整っています。JAMSTECの観測船やスーパーコンピュータなどの大型施設も、東北大学の研究者が共同で活用できるようになっており、非常に良い連携体制が構築されつつあります。
Text:アイハラケンジ
Photo:三浦晴子
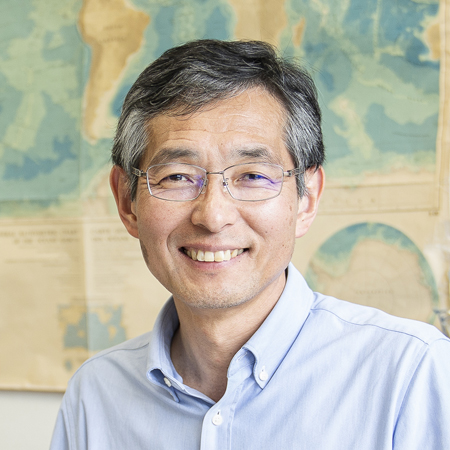
須賀 利雄(すが としお)
東北大学・海洋研究開発機構 変動海洋エコシステム高等研究所長、大学院理学研究科教授。海洋研究開発機構上席研究員を兼務。理学博士。主な研究分野は海洋物理学。国際アルゴ計画に開始時から参加し、アルゴ運営チームの共同議長も務めた。UNESCO/IOC「全球海洋観測システム」運営委員会コアメンバー、IPCC「海洋・雪氷圏特別報告書」代表執筆者などを歴任。













