
海洋生態系という「いのち」をめぐって(3)
─ 海は「いのち」 ─
須賀利雄(WPI-AIMEC所長・東北大学大学院理学研究科 教授)
2025.9.12 Fri
2024年に東北大学と海洋研究開発機構(JAMSTEC:ジャムステック)が共同で設立した「変動海洋エコシステム高等研究所」(以下、WPI-AIMEC:ダブリューピーアイエイメック)は、海洋に存在する⽣態系に焦点をあて、学際的なアプローチにより、海洋⽣態系の維持に重要な連動性・安定性・適応性の理解を深化させ、人間社会に役立つ、海洋⽣態系の変動予測の実現を目指す研究所です。
地球の表面の約7割は海が占めていることからもわかる通り、海を理解することは、地球の環境はもとより、私たち人間、そしてあらゆる生命(いのち)を理解することと、ニアリーイコールなのかもしれません。
今回は、WPI-AIMEC所長の須賀利雄先生に、海と人間との話題をきっかけに、海とあらゆる生命(いのち)との関係性について、お話を伺いました。
お話をお伺いして、WPI-AIMECが海に関する様々な分野を横断する組織ということが理解できました。そこに医療や医学の領域がクロスする部分というのはあるのでしょうか。
須賀
大きな枠組みでいえば、私たちの研究は、地球環境がどのように維持されているのか? を理解しつつ、それを人間活動の持続性に繋げていくことを目指しています。その中で、海が非常に重要な役割を果たしているため、その理解を深めようとしているわけです。これは、医療や医学の観点でいえば、「命」というテーマとも自ずと関わってくるでしょう。また、分子レベル、遺伝子レベルでの生き物の応答を扱う研究者もいて、私はその分野には詳しくありませんが、微生物と人間という、一見かけ離れた存在の間にも、なにか通底するものがありそうです。その意味では十分に医療や医学とクロスする部分があると思います。
少し抽象的な話をしますと、私自身が以前から感じているのは、海の循環と人間の血液循環との類似性です。血液は、酸素や栄養を体中に運び、同時に老廃物を回収していく、生命維持に欠かせない輸送システムです。海の循環も、まさにそれに似ていて、たとえば黒潮のような強い海流は、動脈のように海水を力強く運んでいます。
海では、低緯度の地域に太陽のエネルギーが多く降り注ぎますが、極地ではその量が少なく、エネルギーが不足しています。そこで、地球全体のバランスを保つために、海と大気が協力して熱を高緯度へ運んでいるのです。割合でいえば、大気が2に対して海が1くらいですが、たとえば熱帯から日本周辺のような中緯度域までは、海が主役として熱を運んでいます。冬になると、黒潮が運んできた暖かい海水は、冷たい季節風にさらされて冷やされますが、これは逆に言えば、海が大気を温めている、あるいは、海から大気に熱をバトンタッチしているとも言えるのです。
さらに、海の内部では、表層で冷やされた海水が沈み込み、深海をゆっくりと流れていきます。そして、深いところでじわじわと温められながら、少しずつ表層へと戻ってくる ―この動きもまた、血液の動脈と静脈に似ています。
この循環は、単に水を動かしているだけではありません。酸素や栄養塩を運び、生物の生存環境を形づくる非常に大切なプロセスです。たとえば、深海にたまった栄養塩が、温められた水とともに表層へ上昇することで、植物プランクトンが再び活動できる環境が維持されます。
このように考えると、地球全体を1つの「生命体」としてとらえた場合、海の循環は、まるでその血液のように働いているといえるのではないでしょうか。酸素や栄養を運び、老廃物を回収し、また再び循環させる。こうした働きが、今の海洋生態系を支えているのです。
ただし、現在の生態系は、あくまで今の海の環境に適応して成り立っています。つまり、熱の分布や酸素、栄養塩の供給といった物理環境にあわせて、長い時間をかけて進化してきたのです。一方で、その生態系自体も、環境に影響を与えています。生物と物理環境の相互作用は非常に複雑で、どちらか一方だけでは説明しきれません。
私たちの研究の目的は、まさにその複雑な関係性をひも解くことにあります。海の循環がどう成り立ち、それがどのように生態系に影響を与え、そしてまた生物がその環境にどう応答し、影響を与えているのか。分子レベルから地球規模のプロセスまでをつなげて理解するということです。
いわば、海自体が一つの生命(いのち)でもあり、その海が様々な生命(いのち)を支えているということですね。
須賀
そうですね。地球全体の海を「One Ocean」(ワン・オーシャン)として捉えるというのは、海を1つのシステムとして理解するということです。つまり、すべての海はつながっていて、グローバルなスケールで見ると、海は統一的な循環や構造を持つ「ひとつの生命体」のような存在だと考えることができます。
ただし、その中をより細かく見ていくと、各所に独自の環境が形成されており、その環境に適応した多様な生き物たちが、それぞれのニッチ(生態的地位)1で生きています。つまり、海はグローバルな統一性を持ちながらも、同時に非常に複雑で階層的な構造を持っているのです。このように大きなスケールと細かなスケールの両方をつなぎ合わせて、海というシステム全体を「生命」として捉え、統合的に理解していくことが、私たちが目指していることなのかもしれません。

地球温暖化の話題が出て久しいですが、その地球温暖化によって、海に存在するさまざまな生命も危機的な状況になっているといえるのでしょうか。
須賀
今存在している海の生態系は、現在の海の環境 ―たとえば海の循環や温度分布など― に適応して成り立っています。言い換えれば、生態系はその環境と一体になって存在しているのです。ですから、そうした環境が大きく変わってしまうと、現在の生態系にとっては望ましくない影響が及ぶことになります。生き物によっては生息域を移動せざるを得なくなることも考えられますし、場合によっては、一部の生き物が死滅してしまうかもしれません。
こうした変化が連鎖的に起こることで、生物多様性が失われたり、生態系の構造そのものが変わってしまう可能性もあります。ただし、現在の温暖化のペースにおいて、すべての生命が消滅してしまうというような極端な事態が、すぐに起こるとは考えにくいと思います。
とすると、海に暮らす生命は意外とタフなんでしょうか? 現在の環境に「適応」していくということでしょうか。
須賀
過去には「生物の大量絶滅」が実際に起きたことがあります。数億年前には、地球規模で多くの生物が一度に姿を消した時期が何度かありました。それらは、地層の堆積物などに痕跡として記録されており、地質学的にも確認されています。現在の温暖化がこのまま進んでいけば、そうした過去の大量絶滅に近い現象が将来的に起こるのではないかと懸念する声もあります。ただし、それが100年、200年といった近い将来に起こるかどうかは、まだ不確かです。
今海で生きている生物たちにとって、現在進行中の環境の変化は、やはり大きな問題になると思います。特に、自分で移動できない生き物たち ―たとえば根を張って生息するような生物にとっては致命的です。その代表的な例がサンゴです。温暖化の影響によって「白化現象」が起こり、サンゴは大規模に死滅しつつあります。これはすでに各地で現実に起きていることで、非常に深刻な問題です。
一方で、変化した環境に適応しながら生き延びていく生物も、きっといるはずです。これが、私たちが先ほど触れた「応答」と「適応」のうちの、まさに「適応」にあたる部分です。これから50年、100年という時間の中で、環境が大きく変化していく間に、生き物たちがどのように適応していくのか。そのメカニズムを理解していくことも、非常に重要な課題です。
ただし、現在の温暖化は、自然界が過去に経験してきた変化のスピードと比べると、あまりにも速すぎるのです。おそらく数百倍、あるいは数万倍のスピードで進行していると言っても過言ではありません。これまでにも、地球は温暖化や寒冷化を繰り返してきましたし、海に溶け込む炭素の量(したがってpH)も増減してきました。しかし、それらの変化は、数万年単位、あるいはもっと長い時間をかけてゆっくりと起きていたのです。
ところが今は、わずか数十年という短期間で、劇的な変化が起きています。私たち人間が一生のうちに、これだけの変化を実際に体感している ―それほどまでに急激なのです。
こうした変化のスピードは、これまでの地球の歴史の中でも前例のないものであり、生物がどこまで適応できるのかは、まだ十分に理解されていません。ですから、今私たちが直面している変化に対して、生物がどのように応答するのかを解明することは、これからの科学にとっても非常に大きなテーマの一つだといえるでしょう。
地球温暖化で地球に溜まってしまった熱のほとんどを、海がカバーしてあげているという話題を聞いたことがあります。海は地球のケアラーであるとも言えるのでしょうか。
須賀
海水というのは、熱しにくく冷めにくいという性質を持っています。物理的な言葉で言えば「熱容量が大きい」ということです。この性質が、いわばクッションのような役割を果たし、地球全体の温度変化を和らげています。
現在の地球温暖化は、主に温室効果ガスの増加によって引き起こされています。もともと地球では、太陽からの放射エネルギーと、地球から宇宙に放出される赤外線のエネルギーがほぼ釣り合っていました。しかし、温室効果ガスが増えることで、赤外線が宇宙へ放出されにくくなりました。
なぜなら、温室効果ガスは赤外線を吸収し、再放出しますが、それらは地表よりも低温のため、放出される赤外線の量は少なくなるからです。結果として、地球が受け取る太陽エネルギーと放出する赤外線との間に不均衡が生じ、余剰のエネルギー(=熱)が地球に蓄積されていくのです。こうした蓄積は産業革命以降進んできましたが、ここ数十年はそのスピードが非常に速く、観測でも明確に確認されるようになっています。
その「蓄積された熱」がどこに行っているのか ―この問いに対して、かつては海の内部はよく分かっていませんでしたので明確に答えることができませんでした。しかし、先述した「アルゴ」の観測システムによって、熱の行方について、この20年でかなり明らかになってきました。
データによれば、過去50年間に地球がため込んだ熱のうち、90%程度が海に蓄えられていたことが分かっています。大気に蓄積されたのは、全体のわずか1〜2%程度です。つまり、私たちが現在「気温の上昇」として感じている温暖化は、実は地球全体が蓄積してきた過剰な熱のほんの一部にすぎません。もし、海がその熱を吸収していなかったとしたら、大気の温度上昇は今よりはるかに深刻だったでしょう。
ここで注意すべきは、海が太陽からの熱を直接吸収できるのは表層だけだということです。表層で熱を吸収した水を深いところまで沈めていかない限り、海はそれ以上の熱を蓄えることができません。ですから、表層の海水がどのように深部へと運ばれるのか ―つまり、海の循環構造を理解することが、地球の熱収支を把握する上でも重要なのです。
もう一つ大事なのは、二酸化炭素(CO₂)の吸収についてです。人間の活動によって排出されたCO₂のうち、約3分の1から4分の1は海が吸収してきたとされています。
この吸収には、海水に物理的にCO₂が溶け込むというプロセスだけでなく、植物プランクトンによる光合成も深く関わっています。光合成によって、大気から海に溶け込んだCO₂が植物プランクトンの体(有機炭素)を作り、一部は食物連鎖を通じて深海へと沈降していきます。もしその有機炭素が深海に長期間とどまれば、CO₂を「隔離」したことになります。このプロセスを「生物ポンプ」(Biological Pump)と呼びます。海がCO₂を吸収・貯留する上で、生物の役割は非常に大きいのです。
しかし、このプロセスが今後も同じように続くのかどうかは分かっていません。今のように海がCO₂を吸収してくれている間はよいのですが、もしある時点でそのプロセスが弱まり、逆に海がCO₂を放出し始めたとしたら、状況は一変します。また、今後、人類がCO₂排出を削減していくことで大気中の濃度が下がっていった場合に、海との濃度差が小さくなった結果どうなるのか ―この点についても、まだ十分には分かっていません。現在は、全体として大気中のCO₂濃度の方が高いため、海に溶け込む仕組みが働いていますが、将来的にそのバランスが逆転する可能性もあるのです。ですから、海の生態系がどのように機能し、CO₂の吸収にどう関与しているのかを正しく理解することは、気候変動を見通す上でも必要不可欠なのです。
Text:アイハラケンジ
Photo:三浦晴子
- 生態的地位(ニッチ):生物が属する生物群集や生態系の中で占める役割や地位のこと。食物連鎖における位置や他生物との競争関係、生息場所、活動時間など、その生物が生き残るために必要な環境要因や資源利用の仕方をさす。 ↩︎
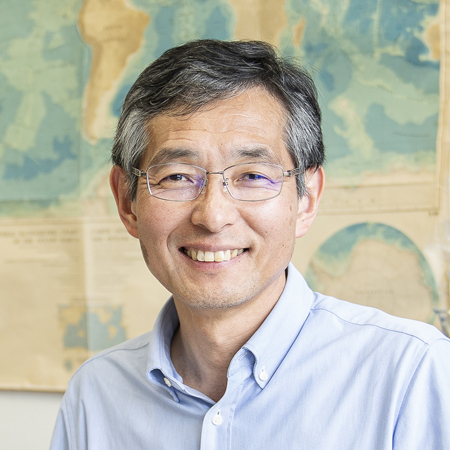
須賀 利雄(すが としお)
東北大学・海洋研究開発機構 変動海洋エコシステム高等研究所長、大学院理学研究科教授。海洋研究開発機構上席研究員を兼務。理学博士。主な研究分野は海洋物理学。国際アルゴ計画に開始時から参加し、アルゴ運営チームの共同議長も務めた。UNESCO/IOC「全球海洋観測システム」運営委員会コアメンバー、IPCC「海洋・雪氷圏特別報告書」代表執筆者などを歴任。













