
「生命のつながり」と未来へのまなざし(後編)
宇宙飛行士・毛利衛 × 張替秀郎(東北大学病院長)× 石井直人(東北大学医学部長・医学系研究科長)
2025.3.27 Thu
スペースシャトル・エンデバー号に搭乗し、1992年と2000年の2回にわたって宇宙実験や地球観測をおこなった宇宙飛行士・毛利衛さんは、その当時から現在に至るまで一貫して、「生命のつながり」について語ってこられました。
今回の鼎談では、宇宙から地球を見つめたという経験によって生まれたその独自の生命観について、毛利さんにお話しいただきつつ、張替秀郎・東北大学病院長と石井直人・東北大学大学院医学系研究科長・医学部長とともにライフサイエンスの現在と未来について、そして希望について、若い世代の皆さんへの想いについて語っていただきます。
張替
宇宙から地球をご覧になった経験から、毛利さんは「全体を見る」という俯瞰的な視点を強くお持ちだと思います。あらためて、毛利さんの生命観についてお聞かせいただけますか。
毛利
私には「なぜ地球に生命が生まれたのだろう」という疑問がありました。宇宙は真空で、ふつうの生命は生きることができない環境です。私は、そんななかで、完全に人工的に科学技術によってつくられた宇宙船という生命維持装置のなかから、丸い地球だけが青く輝いているのを見ました。地球の姿を見た宇宙飛行士はみな例外なく「美しい」と言いますが、それはいったいなぜなのか考えてみると、自分が帰ることのできる場所はそこにしかない、と実感するからだと思います。そしてまた、宇宙から見ると、地球というのは「ありがたい」ものであると感じます。そこに帰れば、空気も水もあり、すべての生き物が宇宙服を着ることなく生身のままに生きられる環境があるからです。
また、宇宙から地球を見ることは、長いスパンを感じることでもあります。生命はそこで生き、そこでしか生きられません。いまの自分があるのは、いろんな生命が生まれて、多様化して、なかには絶滅した生物もいて、そして現在の地球上には5000万種とも言われる種が生きていて、そのような生命のつながりの一つとして自分がいる、と感じられるからです。ヒトゲノム解読によって明らかになったのは、人間というのはなんら特別ではなく、遺伝子の長さや配列がちょっと違うだけで、他の生物とほとんど変わらないということでした。
20世紀後半まで人間は、生きるための環境が無限だと思ってきたわけですが、その地球環境が人間の存在によってかなり変わってきてしまいました。今世紀、世界の人口は急速に増え続け80億人を超えました。人間がこれから生き延びるためにはどうしたらいいか、真剣に考えなければならないところまで来ています。私は宇宙から、太陽が当たっていない夜の地球を見ましたが、そこにあったのはどの大陸にもたくさんのオレンジの光がびっしりと灯っている光景でした。もうすでに限界のように見えるのに、これから100億人にまで増えようとしているというのは果たして可能なのだろうかと思いました。

21世紀後半には103億人に到達してピークを迎え、そして徐々に減っていく、という国連の将来予測があります。しかし、私は、もっと急激に、激減してしまうのでは、と危惧しています。人類だけがこの地球に急増すれば無理が生じて、自然はバランスを取り戻さざるを得ない状況になるのではないか、と思うからです。それでも人間は、お互いに我慢して譲り合うことで生き延びられる可能性があるはずです。にもかかわらず、現実は、国というものが邪魔をして、ぶん取り合戦をはじめています。世界として大事なのは、100億人までなんとか我慢して、100億人で生き延びる、サバイバルするということ。そして、地球生命として全うすることだと思います。生命が、永遠に生きようなんてありえませんから、全うする、ということが大切です。
ただし、AIによって新しい生命をつくりだそうという動きもあります。人間をさらに長く生き延びさせるとか、オリンピック金メダルをさらに取るために子どもの頃に遺伝子を操作して筋肉量を増やすとか、そういうことが可能になっています。さらには新しい生命もつくれてしまうという時代ですので、きっとAIを武器にした「超人間」が生まれるのではないか、と思いますね。
石井
世界の人口がピーク後に激減するのではないか、というお話ですが、様々な環境破壊であるとか、地球そのものに狂いが生じることによって、もうこれ以上耐えられない限界を迎えて、そうしたことが起こりうるのであれば、やはり、その前になにか手を打たないといけないでしょう。我々の世代よりも若い次の世代に、その危機感も含めて受け継いでもらって、人類が滅びないためのなんらかの方法を模索しなければならないのではないでしょうか。
そのとき、AIは、ヒントとして使える可能性があるように思います。先ほど「超人間」というお話がありましたが、人類が滅びるのを克服するという意味合いでの「超人間」というのも、もしかすればAIに設計してもらって教育に生かす、などということもありうるのでは、と。AIと、次世代を育成することと、人類が生き延びることと、どのように考えたらいいのでしょう。

毛利
国のエゴに任せてしまうと、自国だけを繁栄させよう、という動きが出てきます。ほんのすこし前、21世紀を迎えたばかりの頃は、様々な国々がグローバルな視点から「みんなでどうしていったらいいのか」を共に考える時代でした。おそらく、それが行き過ぎて、不満層がずいぶん出てしまって、現在のようになっているのでしょう。長い目で見れば、現在は過渡期ということだろうと思います。
科学技術の進展によって、AIはやがて人間をコントロールするようになるかもしれない、ということが現実味を帯びてきていますが、そのことについて私はポジティブに捉えています。国連で200もの国々が議論をしたり投票したりしても想いが一致せず、なにも解決しません。けれど、科学的データをもとにAIが将来予測することによって、どの国からも文句がでることなく合意を得ることができる可能性があるだろうと思います。AIがプラスに働く役割というのもきっとあるはずです。
以前、サウジアラビアで科学技術の今後のありかたについて講演したとき、若い人から「ここは石油の国で、ビジネスも儲けのために動くから、CO2排出のコントロールはきっと難しい。いったいどうしたらいいですか」という質問がありました。そこで「みなさんは宗教を非常に大切されていて、アラーは絶対ですよね。またみなさんは、科学的事実を積み重ねたものを理解し、納得して従いますよね。であれば、AIがアラーのようになればいいのではないでしょうか」とお答えしたところ、サウジアラビアの若い人たちはとても喜んでくれました。多くの人たちがいまたくさんの情報に囲まれて不安を抱えていますが、「ディープラーニングから得られた高度な智恵がこう予測しているよ」と言われたら、それに従うことも可能だろうと思います。

石井
そうかもしれませんね。サイエンスはあまりにも情報が膨大なので、それをもう AI に整理してもらって、そこから未来が予測できるのだろうな、と、お話を伺って思いました。その智恵を人類みんなで共有できれば、自ずとなにが危機なのか、それをどう避けるのかっていうのは見えるのかもしれないなと非常にポジティブに感じたところです。
張替
国の思惑はそれぞれあるでしょうが、私たち医者にはそれを変えることはできません。私たちがやれることは、患者さんを診る、というただそれだけです。患者さんが亡くなると、それまであたたかかった体が急に冷たくなって、ただの細胞の塊になり、生命というのは有限なものであることを感じます。死はいつ訪れるかわからないし、とめようもありません。生命をただ永遠に延ばそうというのは医療として考えていくべき方向ではないと思います。私たちは、だから、その瞬間まで、できるだけ健康に社会生活を送っていただいて、苦しむことなく最期を迎えていただく、ということのサポートをするだけです。ある意味、そこから先、冷たくなっていくのを迎えるのはしかたのないことであり、人工的に「超人間」として生き延びることは、たぶん私たちは考えていません。
とはいえ、実際のところ、情報やAIというものが医療に関わってくるのもまた間違いのないことです。おそらく、細胞から人の個体をバーチャルでつくりあげることもできますし、どこが悪くなるとどういう病気になるかもまたバーチャルでわかるようになってくるでしょう。医療の発展には間違いなく必要ですし、それを使って医療のゴールを目指すというのが私たちの仕事なのかなと思います。
毛利
患者さんによっては、末期状態でありながら生命維持装置によって息だけはしている、という状態で生かすこともできますよね。日本人の場合、あたたかみを持って生きていれば「それをいつまでも続けさせたい」と思うのも心情のような気がします。そこの「死」と「生」との患者さんやその親類のかたたちが、なかなか納得できない部分もあるでしょうね。
張替
そこは、お一人ひとり人生も、家族も、親類も違うわけですから、決断は色々です。けれども、やはりその状態であっても、人工呼吸器をつけても、そこには限界があって、いずれは亡くなるときがきます。そこをどこで止めるかは、それぞれの人生観や哲学などによるでしょう。そこにおいても、生命は有限であり、いずれどこかで終わるというのは同じではないか、と思います。
毛利
おそらくそこの部分が、お医者さんの人材育成において非常に重要なところなのでしょうね。
張替
そうですね。すごく大事なところです。
毛利
生と死にどう向き合うのか、人の気持ちをどれだけ理解するか、ということなのでしょうね。

張替
最後に、毛利さんから、ぜひ若い人たちに向けてメッセージをいただけたら、と思います。
毛利
東日本大震災後、日本科学未来館の科学コミュニケーターたちは自分たちになにかできるかを考え、被災地に向かったことがありました。被災者のかたたちに科学と真実を知ってもらうことで、お手伝いできることがあると思ったからです。しかし、福島で「放射線の検知器がありますから大丈夫ですよ」「検知器で調べたのでこの水道水は安全ですよ」と言っても、信じてもらえない、という経験をしました。原子力は100%安全だと言っていたのにそうじゃないじゃなかった、という現実に触れた人たちから「科学の言うことは信じられない」と言われてしまったのです。そんな出来事があってから、では、私たち科学コミュニケーターはこれからどうしたらいいだろうかと考えました。科学をそのまま伝えても、信じるか信じないかの問題になってしまいます。それで辿り着いたのは、社会の一人ひとりに「信頼されるかどうか」だということでした。言った言葉が信頼される人になれるかどうか、がこれから問われるのだと思いました。
私たちはあの大きな震災と事故を経験したことで、信頼というものが簡単に壊れてしまうことを知りました。全ての分野でそれをどう築いていくか、改めて問われることになったのです。お医者さんも含めて、若い人たちには、まずそれを考えていただきたい、と思います。信頼される人間になれるかどうか。きっとお医者さんも、患者さんに向き合うときに問われることになるのはないでしょうか。
石井
本来、医師というのは、その肩書だけで、最初から患者さんに信頼されているところがあります。けれど、信頼を失うのはとても簡単です。なにかをしてしまえば、あっという間に失います。
学生時代に様々な経験をして、友達と付き合って、というなにげない日々から信頼とはなにかを学べるはずですが、今の学生はそういうことも多くないようです。ありきたりですが、やはりたくさんの経験をして、友人たちと大いに一緒に活動するということが、将来的には、医師として、あるいは研究者として、周りからの信頼を得られるような人間になる礎をつくるのだろうと思います。
ですから、できるだけ仲間と遊べ、喧嘩しろ、と常々、教育のなかで学生たちに伝えています。ただ、遊べと言っても遊び方もわからない学生もいますから、もしかしたらもっと人工的にでも教員側からそういう機会をつくったり、仕組みを考えたりしなければならないのかもしれない、と頭を悩ませているところです。
毛利
ある程度失敗はあるもの、というように、失敗を容認しながら学んでもらう、ということも大事かもしれませんね。
張替
石井先生のご心配のとおりに私も感じますが、しかし、自分を振り返ってみると、大学を卒業するときに、そんなに人間的にできていたかというと決してそうでもありませんでした。毛利さんのおっしゃる通り、患者さんに教えられて育つということもありますし、また実際に、人の死に立ち会うことになりますから、そういった経験を積み重ねていくうちにいやがおうでも医師として成長していくだろうと、ちょっと期待して、私は若干楽観的に見ています。
毛利
これからも絶対に無くなることのない職業というのは色々とあるでしょう。医師もそのひとつだと思います。人を治すわけですからね。そういう意味で、様々なものがAIに代わられようとしているなかでも、一人ひとりが大切な仕事を担っている、ということをぜひ誇りにしていただきたいと思います。それが若い人たちに私が伝えたいことですね。
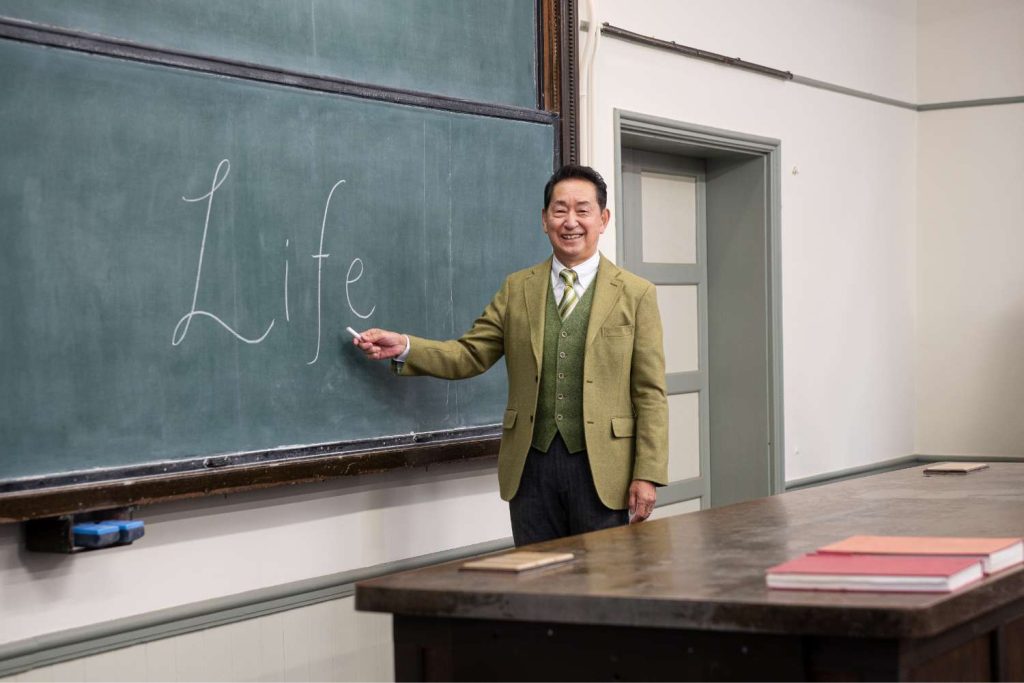
取材日:2025.1.22
場所:東北大学片平キャンパス 魯迅の階段教室にて
TEXT/LIFE編集室
PHOTO/三浦晴子

毛利 衛
Mohri Mamoru
1948年北海道生まれ。北海道大学大学院理学系研究科修士課程終了。南オーストラリア州立フリンダース大学大学院博士課程終了。理学博士。北海道大学工学部助教授を経て、1985年に日本人初の宇宙飛行士候補に選抜される。1992年と2000年にスペースシャトル・エンデバー号で宇宙実験や地球観測を行う。2000年、日本科学未来館の初代館長に就任。主な著書に『宇宙からの贈りもの』『宇宙から学ぶ ユニバソロジのすすめ』(岩波書店)、『日本人のための科学論』(PHP研究所)『わたしの宮沢賢治 地球生命の未来圏』(ソレイユ出版)などがある。
内閣総理大臣顕彰、フランス・レジオンドヌール勲章、藤村歴程賞など受賞多数。

張替 秀郎
Harigae Hideo
東北大学病院長。
1986年東北大学医学部卒業。東北大学医学部第二内科医員、米国ロックフェラー大学博士研究員を経て、2007年東北大学大学院医学系研究科血液免疫病学分野教授。2023年より現職。2024年より東北大学理事・副学長(広報・医療・共創戦略担当)を務める。

石井 直人
Ishii Naoto
東北大学大学院 医学系研究科長・医学部長。
1989年東北大学医学部卒業。東北大学医学部細菌学教室を経て、2009年東北大学大学院医学系研究科免疫学分野教授。2023年4月より現職。













