
冬の精霊の声を「聴く」
――秋田・にかほ市小滝の来訪神行事について――
石倉敏明
2025.4.28 Mon
〈LIFE〉では、医学や医療に軸足をおきつつも、その領域外のさまざまな学術分野やカルチャーなどと積極的に横断していくことで、〈いのち〉の可能性についてみなさんと一緒に見つめ、ひろげていきたいと考えています。
今回は、秋田公立美術大学准教授・芸術人類学者の石倉敏明さんに、特集テーマである「きく」を手がかりに、東北・秋田の来訪神行事を取り上げながら、地域に息づく自然・文化とわたしたちの心身の健康、そして〈いのち〉との関係性についてご寄稿いただきました。
冬に訪れる精霊たち
秋田や山形、岩手など日本の東北部に継承された小正月行事には、鬼のような奇怪な仮面を被り、獰猛な唸り声を上げて家に乱入する冬の精霊が登場する。男鹿半島のナマハゲが有名だが、それだけではない。たとえば秋田の日本海沿岸部には他にも、ヤマハゲ・アマノハギ・アマメハギ・アマハゲなど、日本列島やユーラシアの他の地域に類似した行事が継承されている1。かつては統一した名称はなく、ナマハゲ・ナモミ・ナモミハギ・ナマハギ・ヤマハギなど、集落ごとに異なる名称で呼ばれていた。そうした祭りに現れる特異な仮面をかぶった存在を、かつて日本の民俗学者 折口信夫は「春来る鬼」や「まれびと」と呼んだのだった2。
内陸部の集落の境に立てられる常設の「人形道祖神」とは対照的に、ナマハゲのような「来訪神」は沿岸部の集落で一年に一度現れる一時的な存在だ。自立する彫像としての人形神はいわば民俗的な空間認識に、一時的に人が仮装する来訪神は、季節的な時間認識にかかわる。こうした仮面の精霊は、鬼とも呼ばれ、神とも呼ばれる両義的な存在である。彼らは歓待(愛好)されるわけでも、拒絶(嫌悪)されるわけでもない。肯定的・否定的感情の間で揺れ動きながら、ただ、里の人びとは新たな季節と一年の始まりを告げるものとして彼らを受け入れ、注意深く接待したり、周到に追い返したりもする。サンタクロースやハロウィーンの怪物たちが祝祭の前夜に訪れるように、彼らもまた、正月や小正月が訪れる直前の時間の裂け目にやってくる。彼らの到来が、のちに訪れる春を予祝し、冬を終わらせる前兆となるのだ。ここではこのような冬季の精霊の祭りを、「来訪神」の儀礼として記述していこう。
秋田県のにかほ市や山形県の遊佐町など鳥海山麓に伝わる行事は、とりわけその古い形態を現在に伝えているようだ。実際に来訪神の行事を訪れてみると、その恐ろしい風貌に触れるより前に、独特の音や声を使って自らの訪問を知らしめる作法があることに気付かされる。雪を踏み締める音。激しく戸を揺らす音。床を叩き、玄関の土を踏み、風を切って侵入する音。雷鳴のような唸り声。それらの全てが一種の複合的なノイズとして、神の来訪を告げる振動体験となる。そして、とりわけ子どもたちはその神に対して泣き声によって反応する。恐ろしい仮面や野生的な装束の持つ視覚的なインパクトは絶大だが、祭りの中ではそうした視覚的要素に先立って、必ず特異なノイズが発生し、家という建築的構造に守られた人びとの暮らしに小さな亀裂が走る。それらの音は、周囲の環境音に混じって響く音にすぎないが、日々の暮らしの外部から聞こえてくる異様な音響であることに違いはない。
遠くない春を予告する音を到来させるのは、仮面の神や精霊だけではなかった。折口のいう「まれびと」とは、集落の境界の外部からやってくる「おとづれ人」であり、地域や文脈によって精霊や妖怪のような仮面仮装の存在を意味することも、祝言や芸能を披露する神人や芸能者などの「ほかい人」を意味することもあった3。集落の居住者にとって、「まれびと」は祝福と畏怖を同時にもたらす異人であり、現実と異界を橋渡しする特別な存在であったと言える。折口は、そのようなまれびとが、冬の厳しい東北の正月に時を定めて家々に現れ、小正月のささやかな祝福と冬から春への季節の更新を担うことに注目した。彼らはまさに音を連れてくる、という意味での「音連れ(おとづれ)人」だった。日本海沿いに位置する北陸や東北には、三味線や太鼓を演奏して各地を旅する門付け芸の伝統が比較的最近まで生きており、その担い手は盲目や目に障がいを持つ人たちであることも珍しくなかった。彼らは故郷から遠く離れた地域まで放浪し、集落を門付けしてまわった。
「ほかい人」の鳴らす弦楽器や尺八・太鼓といった簡素な楽器は、日本列島に潜在する古層の芸能から生まれる音であり、神話的な記憶を呼び覚ます音でもある。「ほかい人」は、目に見えない世界に触れる能力のある聖なる芸能者であり、それゆえに優れた歌や楽器演奏といった音楽的才能によって「神のおとづれ」を体現するもの、とみなされたのだ。古代日本語では、万物は音を伴って流動し、その音が自然界に内在する神の活動や移動をあらわすもの、と考えられた。だから、風に揺れる樹々の葉ずれの音も、打ち付ける雨や空を切り裂く雷鳴の音も、同じように音による神々の示現として受け止められた。同様に、素朴な弦楽器や打楽器を伴って家の軒先で披露される歌や漫才も、「ほかい人」の優れた技芸であると同時に、彼らが体現する神々の声として聴取されていたのである。
仮面仮装の来訪神の場合も、実は彼らの世界が視覚的なイメージだけではなく、むしろ繊細な音響感覚や、襖や障子を勢いよく開けて部屋に雪崩れ込んでゆく荒々しいパフォーマンスにこそ、儀礼としての意義があることがわかる。実際に来訪神行事に随行してみると、思いがけずその視覚的インパクトにも負けない音の世界に圧倒される。暖かい冬の民家を取り巻く夜の闇は、海や山から吹きつけける激しい吹雪や、深々と降り積もる根雪に取り巻かれた圧倒的な環境音に取り巻かれている。激しい風音が吹き荒ぶ夜も、降り積もる雪が周囲の音を吸収する圧倒的な沈黙の夜も、秋田に暮らす人びとにとってはすでに日常の一部だ。厳冬の小正月は、そうした音響的コントラストが激しい変化に富んだ季節であり、刻々と移り変わる冬の気候は、そのまま来訪神の印象に直結する。
そうした音は、異郷的な楽器の音色や歌い手の声色であるとは限らなかった。奇怪な仮面の下に顔を隠した里人たちも、唸り声や全身を震わせるけたたましい騒音によって新しい時間と一年の到来を予告する、生きた依代である。彼らは、隠された暗闇の中から仮面に穿たれた小さな穴を通じて相手を見つめるが、神を見つめ返す人びとの視線の先にあるのは、人ではなく謎めいた仮面の顔である。そのおそろしい容貌は、単なる視覚的な威嚇というよりも音声・音響的な聴覚体験と一体になってはじめて統一的な意味をなすと言えるだろう。仮面の精霊たちは、部屋の中で団欒する家族を威嚇するように戸口を揺らし、荒々しく大地を踏み鳴らし、ときに地響きのようにも感じられる独特の唸り声を上げながら、騒々しく民家に侵入する。子どもたちはその姿を見て恐れ慄くが、その前に聴こえる騒がしい音や声こそが、この季節行事の核となる体験と言えるかもしれない。

鳥海山麓のアマノハギ
今年(2025年)の年頭はめずらしく晴れの日が多く、小滝集落の「アマノハギ」が来訪する夜には、深夜まで鳥海山の稜線が見えていた。月夜の山の麓に、精霊たちの姿が映える。真冬の吹雪にも似た精霊の唸り声は、秋田の沿岸部に春をもたらすエネルギーを感じさせる。鳥海山の麓の小さな集落の闇夜を突き抜ける真冬のノイズは、この地域に春の平和をもたらす呼び声なのだ。
人びとは来訪神の到来を一方的に受け止めるだけではなく、彼らと交渉し、酒を飲ませ、満足して帰ってもらえるように接待する。厳しい自然の中に放り込まれたこの土地の人間たちは、傲慢に自然を支配するのではなく、かといって自然による支配をただ従順に受け入れるだけでもない。彼らは、ただその多様な力の矛先に対して最大限の注意を払いながら、仮面来訪神が体現している自然を敬い、その下で倫理的な規範を身につけ、他者と共に季節を生きるのである。
アマノハギは敬意に満ちた交渉術によって、荒々しい自然と何とか渡り合ってきたこの地域の生存の歴史を反映しているようにも見える。だから、来訪神儀礼の中核にある演劇的な要素は、相手の声と主張を聞き、逆に自己の声と主張を聞かせる駆け引きとなる。現代の来訪神行事は、親の言うことを聞かないやんちゃな子どもを叱る道徳的な要素が強くなっているが、古い記録や他地域の類似した祭りを見れば、これが決して子どもを従順に飼い慣らすためだけに行われるものではないことがわかる。むしろ、少し年長の子どもになれば、アマノハギを怖がる年少の子どもたちを励まし、積極的にお酒を注いでタフに応答し、大人と同じようにしたたかに知恵を働かせてなんとか神の滞在を短時間で終わらせようと工夫を凝らせる者も出てくる。彼らは恐ろしい風貌の精霊と駆け引きして、「うちの子どもに言うことを聞くように言って聞かせるから、今日のところはおとなしく山へ帰ってけれ」と交渉する頼もしい大人の側に就こうとするのである。
年少の子どもたちにとってみれば、親は恐ろしい風貌の精霊と対等にやり取りして、最後には自分を守ってくれる守護者となる。とはいえ、頼みの綱となる守護者が不甲斐なかったり、自分の日頃の行いが親の神通力さえ及ばないほど気に掛かったりする悪童たちは、ただただ、怯えてその場をやり過ごすしかない。今年のアマノハギでは、親たちがLINEグループのネットワークでアマノハギ役の若者と連絡をとって、事前に訪問先のニーズを調査しているところが大変面白かった。アマノハギの大役を担う二人の大人の男は、案内役の男と一緒に事前にどの程度の強い度合いで子どもたちを怖がらせるのか、そして具体的にどんな行動を改めるように諭すのかという発言の内容まで、注文を受けている。そして、その受注をスマートフォンの画面で確認しながら時間を調整し、おもむろに家に侵入するのである。
かつては、アマノハギはどの家でもお構いなしに荒々しく乱入し、騒々しいノイズを掻き立てながら子どもを脅しつけた。場合によっては手にした袋に子どもを入れて家の外に連れ出し、雪の中でようやく外に出されることもあったという。当時の体験を知る大人たちは、当時のアマノハギ(現在よりもずっと年少で、時代によっては10代の子どもの場合もあったという)がいかに恐ろしく、傍若無人であったかを懐古するものもいる。その後、このような行事に付き合っていくのが面倒で、参加を拒否する家も出てくるようになった。そして今では、ソーシャルメディアを駆使して事前にどれくらいの怖さで子どもを脅すのか、何を言って聞かせるのか、と言うオーダーまで取った上で家々を訪れる時代になっている。これも、ある意味ではハラスメントとギリギリとも言える暴力的なパフォーマンスをトラブルの種にすることなく上演するために必要とされる「脚本」の一部と言っても良いかもしれない。現代の来訪神行事には、ソーシャルメディアを通じた周到な役割の設定と、現地における臨機応変な即興的上演という二つの大きな要件があるのだ。
小滝のアマノハギは、現在では金峰山神社周辺の小滝集落ばかりではなく、象潟の街中からも「うちにも来てほしい」との依頼を受けて、遠方まで訪れるようになった。そのため、一度集落を回った後に車で海に近い象潟駅方面に出かけ、家だけでなく居酒屋のような依頼先も同様に訪れる。そして、小滝集落に戻ってからも、人々の要望に合わせて、非常に丁寧にコミュニケーションをとりながら、家々を襲うのである。小滝のアマノハギ面は、夏には小滝番楽の鬼人面として、坂上田村麻呂に征伐される蝦夷や、同じく渡辺綱に対峙される大江山の酒呑童子を表すのに使われている。そうした、英雄的存在によって駆逐される鬼人が、厳冬期には威厳と共に祝福をもたらす来訪神となって、集落に回帰するのである。石名坂のアマノハギは、より小規模に近隣をまわるだけだが、それでも基本的な構造は変わらない。こちらは荒々しい木の根っこをもとに作ったアノニマスな顔で、ある意味では日常生活では忘れ去られているような自然の恐ろしさが、この夜だけは外部の闇の中から立ち戻り、家に侵入するかのような幻像を生じさせる。
鳥海山麓の小正月行事に登場するこうした仮面来訪神は、男鹿半島のナマハゲや秋田の他の行事を担う冬の精霊たちがそうであるように、人びとの忌避する自然の恐ろしさや生々しさ、死をもたらす暴力性や残酷性を感じさせる。それは、ある意味では自然災害のような恐ろしい現実にも繋がってくるような近寄りがたい野生のエネルギーを表徴するイメージであり、この行事では騒々しいパフォーマンスを通じて、その隠されたエネルギーが見事に制御されている。さらに、春の大祭、夏のお盆公演を中心として出現する小滝番楽の鬼人面が、真冬には神となって現れるということは、こうした恐ろしい精霊たちの表象が、大和朝廷の歴史的支配によって追いやられ、同化されていった東北の蝦夷の歴史を反映していると解釈することも、決して不可能ではないだろう。
精霊たちは、こうした自然の恐ろしさや災害、死といった負の側面を持つエネルギーを体現しながらも、人びとの配慮と注意によって見事に制御された「回帰する野生」のイメージなのだ。そして、子どもたちは幼少期からこの野生イメージに触れ、それに怯えながらも、徐々に恐ろしさを克服し、精霊と渡り合う交渉術や逞しさを身につける若者に成長する。精霊の声に耳を澄まし、彼らの一挙手一投足を見守る秋田の人びとは、決して人間だけの閉じられた世界で恐ろしい怪物と出会っているのではない。彼らは精霊の背後に生きる世界に耳を澄まし、応答し、交渉することによって、厳冬期の自然が象徴する野生の恐ろしさや厳しさを克服し、来るべき春を予祝する祭りの担い手となるのである。

心身の健康と「共異現実」の構築
最後に、小滝集落における年間を通じた行事の体験を、心身の健康という観点から振り返ってみたい。小滝において年間のはじめに体験される正月行事・小正月行事は一年の更新期というコスモロジーの時間的境界であると同時に、一年間の健康と長寿を祈る予祝の行事でもある。つまり、ナマハゲやアマノハギといった来訪神がやってくることは、単なる度胸試しでも道徳的な示威行為でもなく、何よりも家族全員の健康と平穏な毎日を祈るためのものだ。この点は、秋田の来訪神が部屋に落としていった「ケデ」(ケラ)の藁屑が、ゴミではなく、むしろ一年の無病息災を約束するお守りになるという民間信仰にも現れている。
来訪神は、侵入時には「まめでらか」「達者でな」など、特に年長者に気を遣うものでもある。彼らは親と結託して子どもを脅かすだけではなく、お年寄りの健康を願い、しばしばそれを口にする。小滝集落のアマノハギもまた、高齢化する秋田の地域社会を反映するように、子どもと同居していないお年寄りには特にやさしく声をかけていた。年長者にとってみれば、一年に一度訪れるアマノハギを迎えることは、また一年平穏に年を迎えられたという安心の証でもあるのだ。
一方で、子どもたちにとってみれば、アマノハギの襲来は気が滅入るような出来事である。「金峰神社から、アマノハギ来たぞ~!」と言って家にやってくる恐ろしい来訪神は、例えありがたい精霊であるとわかっていても、そう簡単に心を許すことができるものではない。アマノハギが口にする「ゆうごと聞かねば『ぽっぽら杉』さ連れで行くぞ~!」という常套句は、子どもたちにとっては神聖であると得体の知れない場所でもある金峰神社に連れて行かれてしまう、という脅し文句に他ならない。この地域の人びとは、金峰神社の鳥居から参道の石段を上り、「ぽっぽら杉」という神木や十一面観音が鎮座する宝物殿、その背後に流れる奈曽の白滝と神社本殿を生活空間と隣接する一種の「異界」と認識しているのである。
小滝集落ではで6月の例大祭の日に行われる「延年チョウクライロ舞」という行事を通じて、人びとは慈覚大師が怪物を打ち破って金峰神社を創建したという鳥海山の開山神話に触れ、祝祭的な時間を過ごすことになる。この日の朝、人びとは「当番宿」から「御宝頭」と呼ばれる獅子頭と神輿を運び、神社に移動する。まず当番宿にて笛、太鼓、鉦を鳴らし、獅子舞による「十二段の舞」を披露する。その後、ホラ貝を先頭に、笛、太鼓、鉦を鳴らしながら進み、神社を目指す。チョウクライロ舞は、子どもたちによる可憐な舞(小児の舞、太平楽の舞、祖父祖母の舞)と大人の舞(九舎の舞、荒金の舞、ぬぼこの舞、閻浮の舞)によって構成されている。子どもたち6名からなる舞手は花笠をつけて、顔は白粉と口紅で化粧される。大人は陵王と納曽利の面をつけて双龍の舞楽を舞う。
小滝集落では、来訪神がやってくる冬以外の季節には、春の祭りや夏の盆行事の時期に小滝番楽という娯楽性の強い神楽が上演される。これらは、来訪神儀礼と同様に演劇的要素が強く、とりわけ太鼓や笛による音響と、見事な謡の声が印象的な行事だ。私が訪れた8月の番楽では、小さな子どもたちからその祖父母の世代までがクーラーのない小さな集会所に集まり、青年たちが演舞する番楽の演目に魅了されていた。秋田では、祖霊が異界から戻ってくるというこの夏の季節に、家族や祖先の霊と共に番楽を楽しむというのが、一般的な慣習となっている。
番楽もまた、仮面をかぶり、仮装して舞うパフォーマンスの芸術である。特に平家物語や曽我物語に想を得た中世武士を主人公とする演目は、生々しいほどに有名な歴史物語の一場面を上演する。また、大江山の酒呑童子退治や坂上田村麻呂による蝦夷征伐の上演に喝采を送り、日本列島各地に伝わるローカルな歴史伝承を神話的と言えるくらい見事に演じ切るのである。その時、最前列で食い入るように演者を見つめ、時に手を叩き、時に一緒に踊りながら番楽を楽しむのは、まだ10歳にもならないような、幼い子どもたちである。彼らは、集落の誰が演者であるかを推測しながら、リズミカルな歌や演奏に鼓舞され、役とパフォーマンスに没頭する。そして、その同じ子どもたちが、冬になるとアマノハギの襲来に怯え、泣き叫び、やがてその段階を超えて自らがアマノハギとなる若者に成長していくことになる。
こうして、小滝には冬の来訪神行事(アマノハギ)、春の例大祭とチョウクライロ舞、さらに夏を中心とする冬以外の時期に定期的に行われる小滝番楽による一年のサイクルが浮かび上がってくる。小滝にはこうして、生まれたばかりの赤ん坊から、自らの生を全うするまでこの土地に生きる老人に至るまでの全ての世代に関係する生きた儀礼・祭り・芸能が継承されてきた。小滝の人びとは、多かれ少なかれ、何らかの形でいずれかの行事に関わり、またそれを見聞きして育ってゆくのである。そして、彼らはその中で、能動的に異界から訪れる神々しい存在に触れ、仮面という変身の媒体に憧れるのだ。そうして異界からもたらされる現実を受け止め、異界的存在である精霊や神々になりきることは、おそらく演じる側にとっても、それを鑑賞する側にとっても、「異界からの存在との共存」という特別な意味を持つことになるだろう。それは決して地域社会にとっての「共同幻想」に留まらない。むしろ、それは「共異現実」として共有され、世界観や感受性の深部に影響を与え続けるのだ。私はこのような異界に開かれた集団のあり方を「共異体」と呼んでいる4。
小滝集落において「目の前の世界と異界との共存」という要件が可能になるのは、おそらく集落の中で仮面を身につけて舞を舞うことや踊ること、行事の中で演じることが一体となって、一つの可塑的な現実を構築するからであろう。アマノハギ、チョウクライロ舞、小滝番楽といった出来事の場で出会う仮面の精霊や神々は、決して共同幻想ではなく、むしろ異界と現実が繋がる共異現実を体現する存在なのである。小滝集落に通い、年間を通じてこうした祭りや行事を体験した私にとって、こうした共異現実の生成は、年間を通じた人びとの心理的・身体的な健康に大いに役立っているように感じられた。
私にとって、このような現実構成から得られるある種の活きた知恵は、村澤和多里と村澤真保呂が「べてるの家」の当事者研究と中井久夫やフェリックス・ガタリの思想を架橋して異界的存在論を理論化した画期的な研究『異界の歩き方』に通じるものであった。村澤はこの本の中で、地域に存在するコスモロジーを「人間精神の内部とその外部にある世界や宇宙を結ぶネクサスである5」と論じ、例えば統合失調症患者の当事者研究において個人の患者が体験する幻視や幻聴を「お客さん」として迎え、外在化し、それらと共に生きる技法について語っている。これは、ある意味では日本の民俗社会が仮面来訪神を通じて見えない自然現象や聖なるものを可蝕的・可感的なものに変えてきた技芸と通底する技法なのではないだろうか。
この興味深い研究の中で、村澤は精神医療が個人の脳や神経といった「モノ」と、複雑な出来事の連鎖とネットワークからなる「モノ」とあるいは「プロセス」の両面から患者の状況にアプローチする技術であることを強調している。精神が「モノ」と「コト」の両面を備えていることは、村澤によれば精神医療が「治療」と「ケア」の双方にまたがる領域であり、しかもグレゴリー・ベイトソンのいう「精神の生態学(エコロジー)」として精神医療と文化人類学をつなぐ重要な結節点であるということである6。来訪神行事という目に見えない「コト」もまた、仮面や装束という「モノ」を通じて具現化され、さらに地域の季節や風土を通じて歴史という「コト」と目にみえる対象としての自然や聖地といった「モノ」をつなぐ媒体となってゆく。その意味で、冬の精霊の声を聴くことは、まさに共異現実としてその場に生起する集合的な生命の表現に触れ、共振することを意味するのだ。
村澤の研究はさらに、中井久夫の研究を継承して「宇宙と自己の結びつき(コスモロジー)が危機に瀕したときに、心も危機に陥るということになる」と論じ、近代において分断された「この世界(意識)」と「異界(無意識)」とのつながりを取り戻すことによって、「すぐそばにある異界」を取り戻すことを提案している。村澤はこの「すぐそばにある異界」を単なる虚構や幻想として切り捨てるのではなく、むしろ私たちの生活にとって重要な意味を持つ「ヘテロトピア」として再定義していくことになる。「ヘテロトピア」とは、哲学者のミシェル・フーコーが創案した概念であり、子どもにとっての「庭の奥まった場所」「屋根裏部屋」「両親のダブルベッド」のように想像力を刺激し、新たな現実を懐胎させる場所であるという。私のいう「共異体」や「共異現実」という概念もまた、そのように子どもが人間の外部に存在する異種や異界の物事に触れ、しかも人間性とのつながりを喪失しないままに外部からの刺激を受け止め、着地できるようなコスモロジーのあり方を示している。
私たちが閉じられた医療制度やアカデミズムの中で何かを聴く限り、それは最初から聴きたかった言葉や音が再生されるという予定調和の事態から逃れることは難しい。むしろ、日本列島の東北地方ではいまだに生き続けている来訪神行事のような事例を通して、そうした制度の外に接続し、さらには私たちが「治療」と「ケア」の問題として分断してしまいがちな重要な問題に、再び出会うきっかけが得られるのではないだろうか。もし、私たちが注意深く「共異現実」に耳を傾けるとするならば、それは私たち自身の自意識や価値観に即した対処法を超えて、私たちの外から聞こえてくる無数のポリフォニー的な音声と響きを理解する道筋を探ることにつながっていくに違いない。それはフーコーの言うヘテロトピアとして、今も全ての人の持つ心と命の現実に鳴り響いているはずである。
Photo: 石倉敏明
- 日本とヨーロッパにおける仮面・仮装の精霊についてはアレクサンダー・スラヴィクの『日本文化の古層』(住谷一彦・ヨーゼフ・クライナー訳、未来社、1994年)や岡正雄『異人、その他』(岩波書店、1994年)といった古典的研究のほか、両地域における精霊仮装を撮影したシャルル・フレジェによる作品集『WILDER MANN』(青幻社、2013年)『YOKAI NO SHIMA』(同、2016年)の連作がある。また、筆者による下記のコラムでもこの問題を紹介している。石倉敏明「ナマハゲとサンタクロースは似ている? 世界中にいる『来訪神』の普遍性と地域性」(「まつりと:日本のまつり探検プロジェクト」コラム、URL:https://matsurito.jp/story/202211-raihoshin/index.html) ↩︎
- 折口信夫『折口信夫全集(17)春来る鬼・仇討ちのふおくろあ―民俗学1』中央公論新社、1996年参照。 ↩︎
- 折口信夫『古代研究1 祭りの発生』中公クラシックス、中央公論新社、2002年参照。 ↩︎
- 石倉敏明「魂の共異体としての遠野 遠野巡灯篭木2024に寄せて」『DISTANCE.media』2024.12.13 R2-3(URL:https://distance.media/article/20241209000369/)参照。 ↩︎
- 村澤和多里・村澤真保呂『異界の歩き方 ガタリ・中井久夫・当事者研究』医学書院、2024年、183頁。 ↩︎
- 『異界の歩き方』、第七章参照。 ↩︎
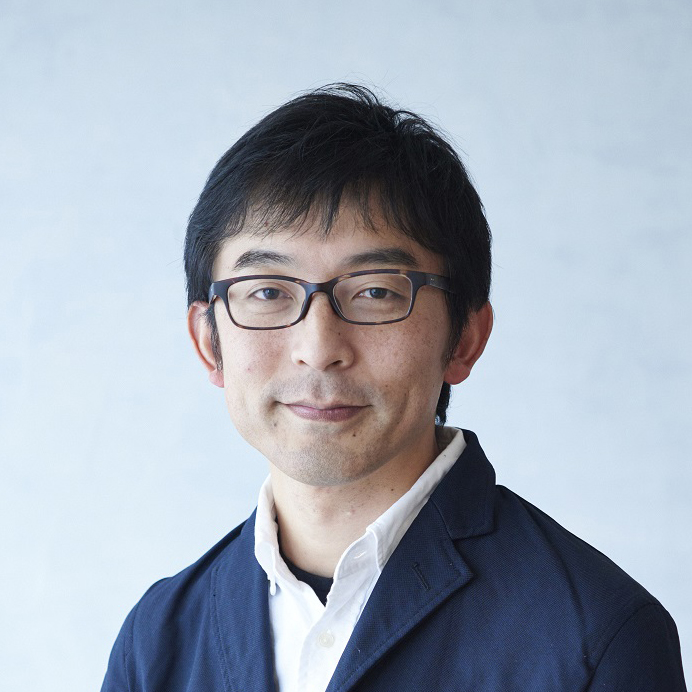
石倉敏明
Toshiaki Ishikura
1974年東京生まれ。芸術人類学者。秋田公立美術大学准教授。シッキム、ダージリン、ネパール、東北日本等でフィールド調査を行い、環太平洋の比較神話学やアーティストとの共同制作をおこなう。2019年、第58回ヴェネチア・ビエンナーレ国際芸術祭日本館展示「Cosmo-Eggs | 宇宙の卵」に参加。共著書に『野生めぐり──列島神話の源流に触れる12の旅』『Lexicon 現代人類学』『モア・ザン・ヒューマン──マルチスピーシーズ人類学と環境人文学』など。













