
「聴こう」としない、力まない。
臨床宗教師・金田諦晃さんインタビュー(3)
2025.4.15 Tue
臨床宗教師をご存知でしょうか。人が死に向き合うことになる現場、たとえば病院や被災地などといった公共空間において、宗教者としての経験を生かしながら、苦悩や悲嘆を抱える人たちに寄り添い、その想いを傾聴し、深く汲み取ろうという活動をされている人たちのことです。
金田諦晃さんは東北大学病院緩和ケア病棟に勤務する臨床宗教師として、これまでたくさんの患者さんたちの想いに心を傾けられてきました。そんな金田さんにとって「聴く」とはどういうことなのか、お話を伺いました。
患者さんから話される内容は、本人のご病気のことが多いでしょうか。
金田
いえ、むしろなんということのない世間話が多いかもしれません。わたしがやっているのは「悩んでおられるかたのところに面談に行く」というようなものではなく、日頃の関わりのなかでお話をお聞きする、というような類のものです。なにげなく語られる季節の話とか、テレビで流れてくるスキャンダルとか、ちょっとした雑談や世間話のなかに、そのかたの人生観とか死生観が滲みでていると感じることはよくあります。こうした、なんということのない会話というのは地域のコミュニティでは当たりまえに交わされていることでしょうが、病院という場所になると会話がどうしても科学的になってしまったり、話題の中心が病気のことばかりになったりしがちですから、なかなか生まれにくいのかなと思うときはあります。話題のポイントがあまりに「悩み」だけにフォーカスされすぎてしまうと、それ以外の部分が見えづらくなってしまうこともあるので、あくまで状況のままに、流れのままにお話を伺うという感じです。
患者さんに語っていただくために意識されていることはありますか。
金田
なにか決まったやりかたがあるわけではありません。はじめて患者さんとお会いするときは、ドクターの回診に付いていってご挨拶をします。そのときには、「いろんな専門の先生も看護師さんもいますけれど、○○さんご自身にしかわからないようなお気持ちや体調というものも絶対にあると思いますから、そういったところからわたしたちも学ばせてもらいながら、お力にできるようなことあれば嬉しいなと思います」とお声がけして、そのかたの経験されていることをわたしたちは最大限尊重しています、ということが伝わるように心がけています。
どうしてもその人にしかわからない経験というものはあるだろうし、どうしてもそのかたの立っているところからしか見えない景色というのもやっぱりあるだろうと思っています。おそらくみなさん、ずっとじぶんの体と心に向き合ってこられて、じぶんの経験していることをそっくりそのまま誰かにわかってもらいたいけれど、それを表現することも難しいし、伝えたくともうまく伝わらないということを、病気されてからの長い経験のなかで感じたり、わかってらっしゃったりするように思います。
実際にお話をお聞きしていると、こちらが気付かされることは多く、またさまざまあります。先日も、長らく入院されていたかたが外出を許可されて紅葉を見てきたというので、「綺麗でしたか?」と尋ねたら、「木と葉っぱの香りがしました」とおっしゃったので、「あぁ、そういう感覚なのか」と驚きました。わたしはてっきり紅葉というのは目で見るものだと思い込んでいましたが、おそらく病院での過ごす時間が長かったことで、より鋭敏に嗅覚で紅葉をお感じになられたのでしょう。
また、絶食の日々を過ごされたのちに緩和病棟に移ってこられたある患者さんは、食事して良いことになって、「『食べていい』って言われて、『生きていてもいい』って言われた気がしたの」とおっしゃって、涙を流されました。
そういうとき、わたしには「あ、この感覚はわからないな」「あ、これは共感できないな」と感じる部分があります。それはやはりそのかたにしかわからない経験なのだろう、完璧な共感は無理だな、と。それに、たとえ共感はできなくとも、相手に寄り添おうとすることはできます。ふだんよく耳にする「ありがとう」とか「お世話になります」という言葉でさえ、それをおっしゃる患者さんと、それを日常的に使っているわたしたちとでは感覚が違ったり、違う次元から発せられたりしているのではないだろうか、と感じることもあります。
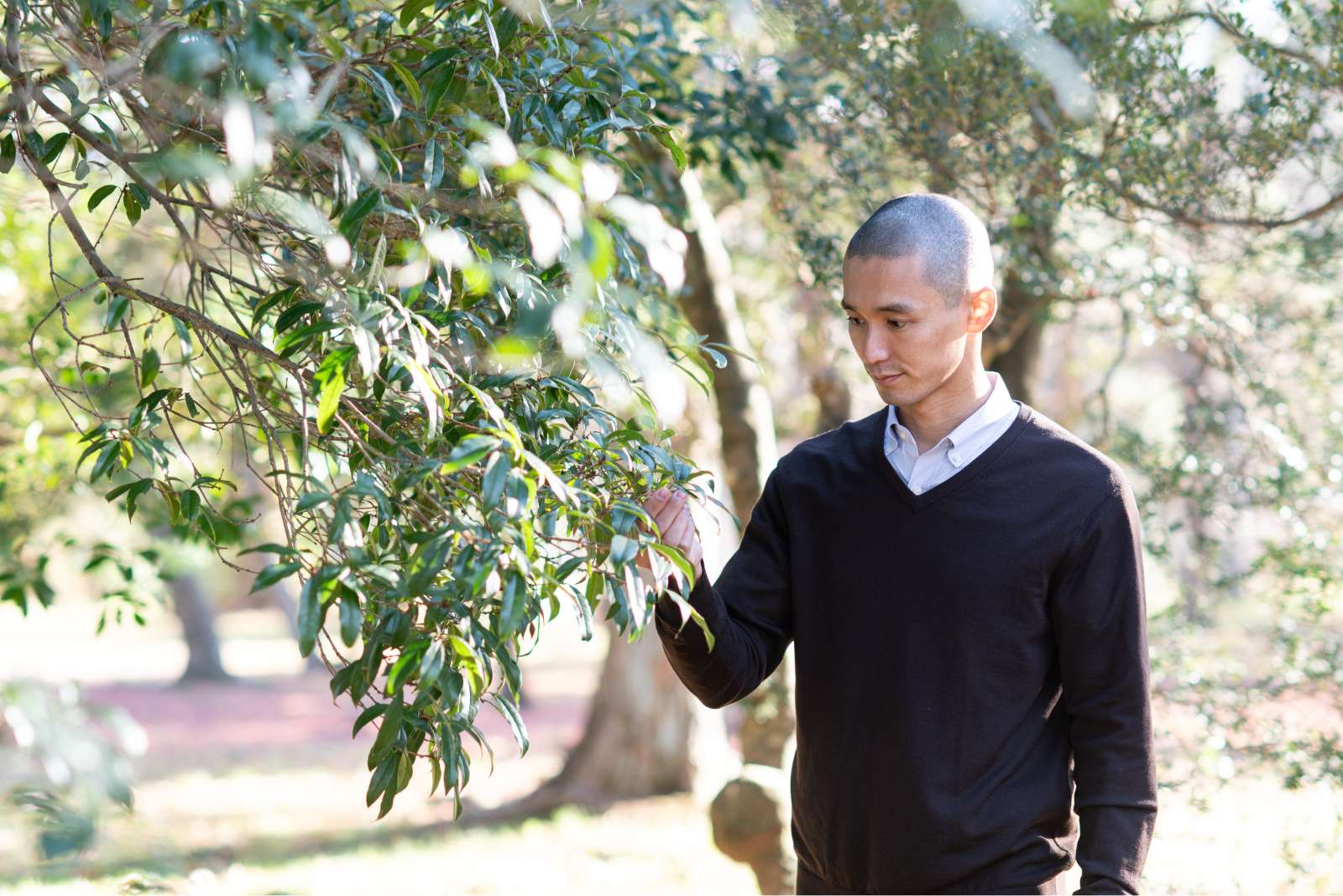
日々たくさんのかたの話に耳を澄ませるのには、相当なエネルギーを必要としそうですね。
金田
よく「力を入れるのは簡単だけど、力を抜くのは難しい」といったことが言われますよね。わたしが大切にしているのも、どちらかというとできるだけ力を抜くことのような気がします。
わたしにとって毎朝の座禅はルーティンのようなものですが、はじめはいろいろなことが駆け巡ります。今日どんな患者さんに会うかな、あの患者さんとお会いしたらどうなるかな、今日はあまり忙しくないといいな、帰宅したとき娘がお昼寝してなかったらどうしようかな……、とさまざまな想念がぐるぐるしているわけです。それではダメだと姿勢を正し、気持ちを整え、今この呼吸に集中しよう、今の体の感じに集中しよう、と意識を向けるうち、だんだんと「今日あれをやんなきゃ!」「誰かをケアしに行かなきゃ!」という高ぶった気持ちが鎮まっていって、「まあ、行ってみればいいか」「あとは導かれるままでいいか」と落ち着いていくのですね。
実際の対話の場面でも、こちらがあまり力みすぎていたり熱すぎたりすると、それが相手に伝わってしまいますし、そうすると「ちょっと…」と警戒されてしまったり、引かれてしまうなどということもよくありますから……
むしろすこし緩いくらいがいい、と?
金田
そうですね。あまり「聴く」ということを意識しすぎると良くないのでは、と思っている部分もあるのです。
たとえば、家族やパートナーに対してなにか想いがあるけれど「これは今ちょっと言いたくない」というときがありますよね。それは、じぶんでわかってはいるけど、あまり向き合いたくないものだったり、言葉にしたくないものだったり、言葉にはなっているけどそれをじぶん自身が認められなかったり、するわけです。人にはそういうような「語りたくない」「話したくない」ときもありますし、どうにも語りづらい状況というのもあるものです。ですから、「語りたくない」とか「あえて聞かない」とかというのもとても大事な態度だと思うのです。
わたし自身、失敗したな、と思うエピソードがあります。それはきっと、あまりにもわたしが「聴く」ことを意識しすぎてしまったがゆえのものだと思うのです。
その患者さんは、体がだいぶ弱くなり、認知機能も衰えてきていました。そのかたのところへ行き「金田です、今日もよろしくお願いしますね」とご挨拶したら、名札をじっと見られて「そうか」という感じで頷かれて、手で合図されたので、その合図通りにベッドを起こすと、窓の外を眺められました。寝ていると窓の外は見えないので「あ、外が見たかったのかな」と思って、わたしもしばらく一緒に眺めていました。窓辺の花瓶に挿してあったひまわりが外を向いていたので、そのかたのほうにそっと向きを変えたら、目をぱっと開かれて、見入ってらっしゃいました。なにも言葉を交わさず黙ったまま、わたしも一緒にお花と外の景色を眺めている……。そんな時間でした。
そこでわたしは「なにか話しかけなきゃ」と思って、「今どんなお気持ちですか?」と声をかけました。そうしたら急にそのかたはソワソワされて、クッションをいじったり、髪を耳にかけるような仕草をされたりして、そしてわたしのほうを向かれて「今日はありがとうございました」という感じで、ベッドを戻して、とアクションをされたのです。
あのとき、なにも声をかけなくて良かったのだな、と後になってから思いました。せっかく居心地のいい穏やかな時間が流れていたのに、不用意なわたしの一言でそれを絶ってしまった、わたしが急に沈黙を破ってしまった、という感触だけが残ってしまいました。
「聴こう」としたために、居心地の良い時間が断ち切られてしまった、と。
金田
そうだと思います。
そういえばかつて、東日本震災後の被災地で、仮設住宅の外で、被災されたかたたちと支援にきた人たちとみんなで焚き火をやったことがありました。ときおり火のなかに焼き芋を入れたりしながら、火を囲って地元の人たちやお坊さんや牧師さんがみんなで喋っていました。その火を囲ってただその場にいて、特になにか意味があるわけではないことをしゃべりながら、ただみんなであったまっている、というような感じでした。あのときのことも、そこに流れている穏やかな時間こそがとても大切なものだったように思い出されます。
そういう場面では、わざわざ「聴こう」という態度も必要はありません。傾聴という技術や専門的な行為を意識しだした途端、かえってそれが壊れてしまうかもしれません。
人というのはおなじ場所で、おなじ時間を過ごして、おなじものを眺めている……ただそれだけでいい、というときがあるのでしょう。わざわざ「語る」とか「聴く」とかしなくとも、ただともに在るというだけで十分、なのではないでしょうか。
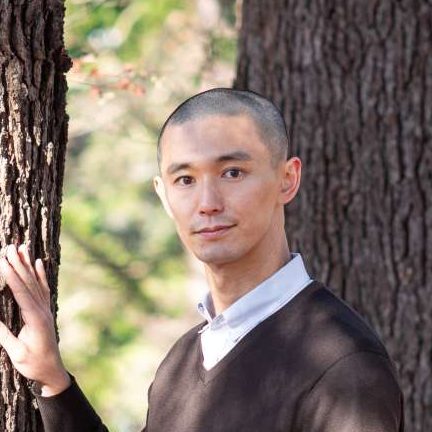
金田諦晃
2012 年駒澤大学仏教学部仏教学科卒業後、曹洞宗大本山永平寺にて安居。通大寺副住職。2016 年から東北大学病院緩和ケア病棟非常勤職員として勤務(認定臨床宗教師)。2019 年東北大学大学院文学研究科博士課程後期入学(死生学・実践宗教学専攻分野)。
Photo : 三浦晴子
Text:空豆みきお(akaoni)













