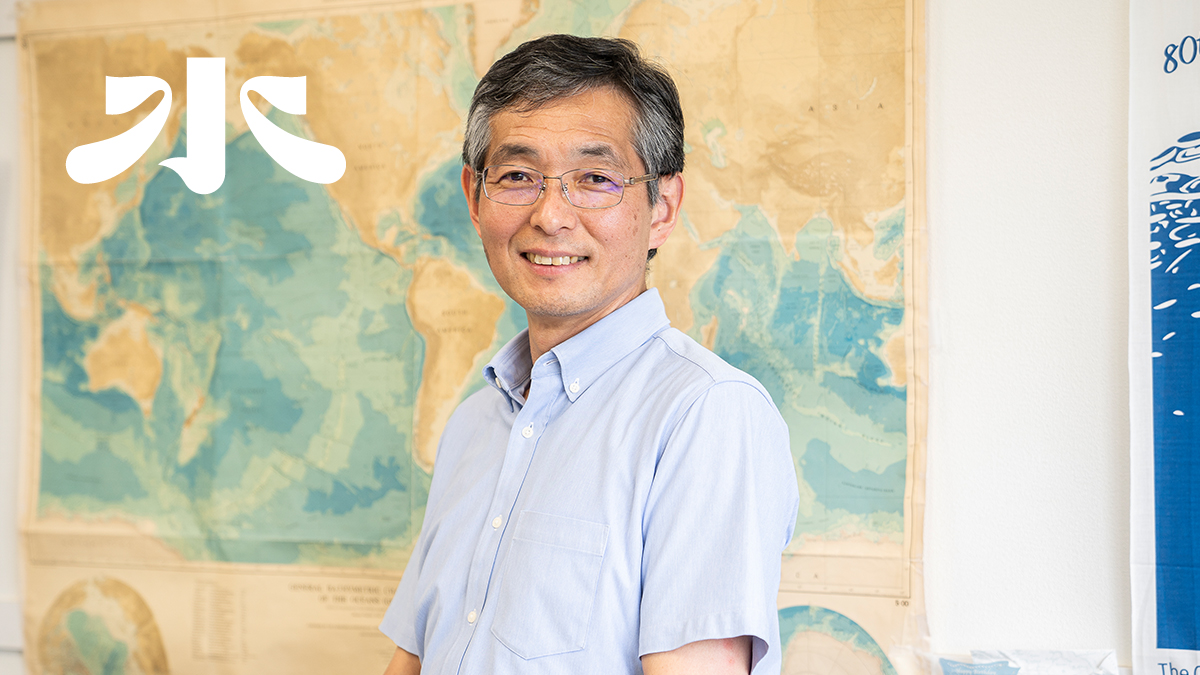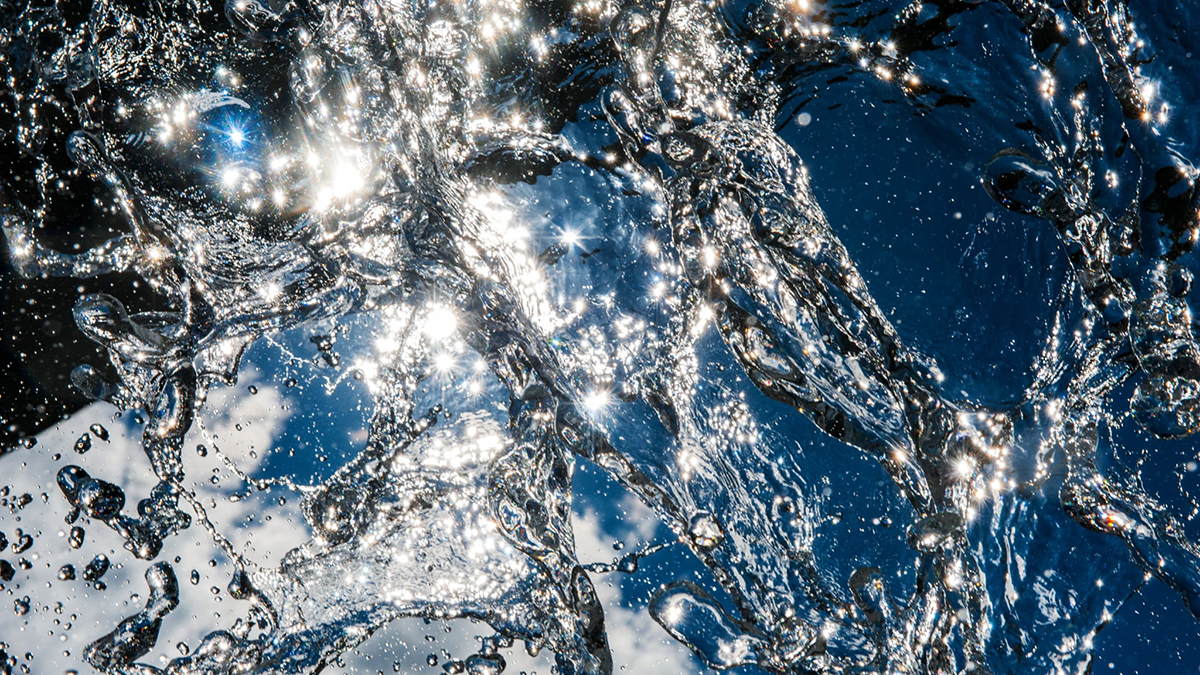多様なバックグラウンドの教員と院生が医療の倫理的問題とその背景について、ディスカッションを通して双方向に学ぶ
2025.3.27 Thu
医療現場における患者さんの
「自由」「自己決定」とは
研究の概要を教えてください
医療倫理・生命倫理は、医療や生命操作に関する技術・制度・政策に伴う倫理的課題を哲学・倫理学、社会学、法学、医学など多様な学問の知見に基づいて検討する学際的な領域です。私の場合は哲学・倫理学をバックグランドとして研究を行っています。例えば、医療を含めた現代社会における基本的な価値観として「自由」や「自己決定」の考え方があります。この考え方は、インフォームド・コンセントやACPといった形で、今日医療現場でも広く受け入れられていますが、他方で、医療の技術の進歩等に伴って「技術の利用(あるいは治療)に関して、どこまで個人(患者さん)の自由な決定に委ねるべきか」といった問題が提起されたりもしています。私のこれまでの研究では主に終末期医療や慢性疾患医療の文脈に焦点を当てて、「“自由である”とはどのようなことか」「なぜそれは大事なのか」「自由を“尊重する”とはどういうことか」といった点を巡る哲学・倫理学の議論を踏まえつつ、この領域における医療者と患者さんのコミュニケーションのあり方、意思決定のあり方について検討してきました。最近は、出生前検査と選択的中絶の文脈に焦点を当てて、この領域における倫理的諸課題の検討をしています。この領域では、近年、母体血だけで胎児の染色体・遺伝子の情報をある程度の精度で調べることができる技術が開発され利用が進んでいますが、他方で、障害者への差別や偏見が助長されることにならないか、過去の優生学や優生思想に結び付くのではないかといった問題が提起されています。私の研究では、「自由」や「自己決定」の考え方に依拠して問題を考えることの限界を踏まえつつ、どのような概念や価値の枠組みに依拠して考えていけばよいのかを検討しています。
問題意識を言葉に表し、
議論通じて互いに学び合う
研究室はどのような雰囲気ですか?
現在は、教員3名(教授、講師、助教)、事務補佐員1名、大学院生8名、研究生1名で構成されています。社会人の方、遠方に住んでいる方や、留学生もいます。各自で研究テーマを設定し、それぞれのペースで研究を進めているため、授業やミーティングがある時以外はとても静かです。定期的に開催している研究室ミーティングでは、教員も含めてお互いの研究進捗(しんちょく)を報告したり、研究に関連する文献紹介を行ったりしています。教員も院生もお互い異なる多様なバックグラウンド(医学、看護学、公衆衛生、薬学、哲学・倫理学など)を持っているため、院生の指摘や発表から学ぶことがとても多いです。医療倫理・生命倫理が学際領域であるということもあり、「教える−学ぶ」の一方向の関係ではなく、お互い学び合う関係の中で教員も院生も研究できるよう、普段から意識しています。
学生にどのようなことを期待しているかなども含め、進学希望者へのメッセージをお願いします
自分の問題意識、特に医療現場で働く中で感じた違和感をまずは言葉に表現してみることがこの領域での研究の出発点だと思います。その意味で、ディスカッションなどにぜひ積極的に関わってもらいたいです。また、臨床倫理コンサルテーションや事例検討に関わってきた私のこれまでの経験から、医療現場の倫理的課題の多くは、実はより広く社会制度や政策全般のゆがみに起因して生じていることが多いと感じています。その点で、学生さんには、さまざまな社会問題に関心を持ち、自分の周りで生じている倫理的課題との関連について思考を巡らせてもらいたいと思っています。
医療倫理を学んだ修了生が
活躍できる場所の広がりに期待
修了後はどのような進路がありますか?また、修了生はどのように活躍していますか?
これまでの修了生は医療関係者が多かったため、主な進路は医療機関です。医療倫理や生命倫理の専門性を生かすことのできる職種は、大学教員や研究者など、とても限られており、残念ながらポストも多くありません。ただ、生命倫理や医療倫理を学んだ医療関係の修了生が今後増えることで、例えば医療倫理コンサルテーションや臨床倫理事例検討など、この領域の活動の重要性についての社会の理解が広まればよいなと思っています。
病院や企業に勤務しながらの修学は可能でしょうか?
個々人の勤務状況によるところが大きいとは思いますが、在籍する大学院生の中には、病院などの医療機関や学校等で勤務しながら研究されている方も多くいます。各院生の時間的ニーズに応じて、ミーティングをオンラインで開催したりゼミやミーティングの時間を調整したりといった対応をしています。
子育てと仕事の両立がしやすい
環境での充実した時間
東北大学の良いところは?
さまざまな点で子育てと仕事(教育・研究)の両立がしやすい環境だと思います。子どもが2人いますが、夫は遠距離通勤をしており、実家も遠方にあるため、平日の子育ては主に私が担っています。それでも何とかやっていけるのは、ひとえに職場の理解と周辺環境(そして家族の協力)のおかげだと思っています。自宅と職場の距離は徒歩で20分ほどですが、その間には保育園をはじめ医療機関やスーパー、学校など、子育てに不可欠なものがそろっていて、子育てには恵まれた環境です。職場も子育てに理解があり、私以外にも子育て中の職員・学生が数名いますが、子ども同伴で研究・勤務をする姿も見られます。2023年度は、子連れで在外研究を行いました。自分の研究だけでなく、子どもたちの現地での学校生活の準備などもあり、大変ではありましたが、とても充実した時間でした。このような機会を持たせてもらい、同僚の先生方には本当に感謝の言葉しかありません。
こけしが好きです。現在の職に就き仙台に住むようになってから、街のあちこちで見かけるこけしにすっかり魅了されてしまいました。気付けば50本ほどのこけしを所有しています。どこが好きかと問われれば、頭の大きい、あえて不安定なシルエットや個々に異なる顔立ちや模様が挙げられます。地震の際は凶器になる可能性があるためたくさん飾れないのが残念なのですが、職場の自分のスペースにもいくつか置いています。時々教務のカウンターにあるこけしを見に行くのも好きです。

2003年、慶應義塾大学大学院文学研究科後期博士課程(哲学・倫理学)満期退学。2013年、慶應義塾大学博士号(哲学)取得。2015年、東北大学大学院医学系研究科医療倫理学分野助教。
インタビュー日:2024年5月28日